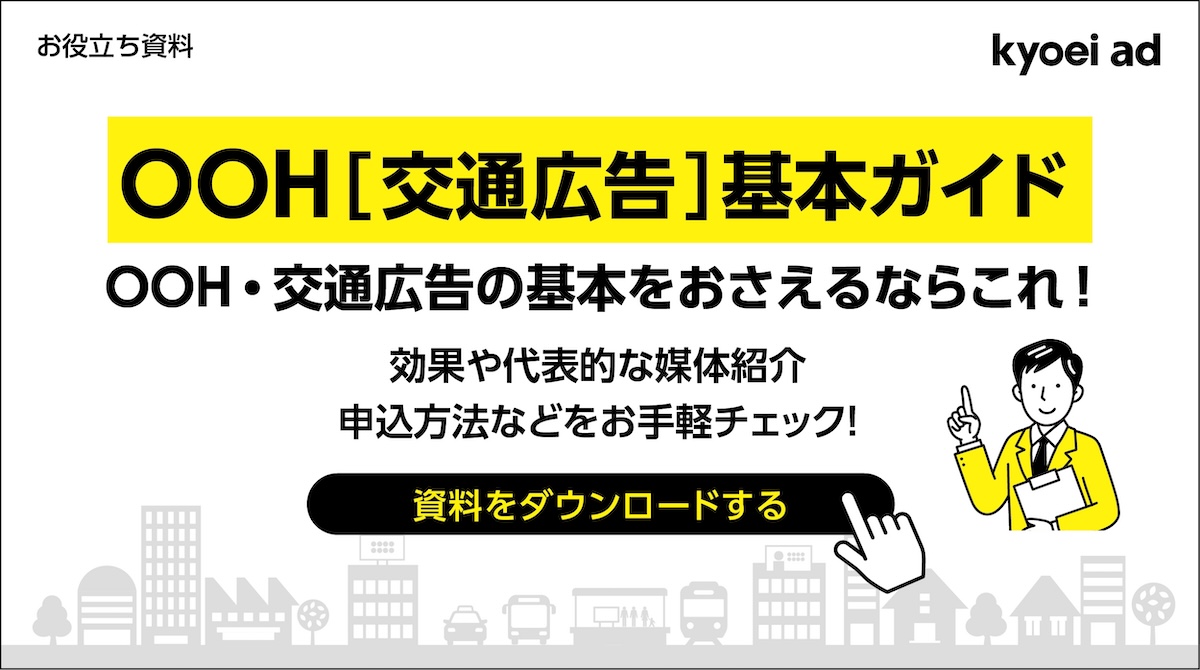2025年10月21日
交通・屋外広告古くて新しい、交通広告のチカラ

朝、駅のホームで目に入るポスター。通勤電車の中吊り広告。
私たちが何気なく見ている広告は、実はとても長い歴史を持っています。
広告は、単なる商品紹介ではありません。
企業やブランドの「想い」を伝え、社会や文化を映し出す鏡です。
この記事では、古代から現代まで続く「広告の歴史」を紐解きながら、私たちが得意とする交通広告の魅力と、未来の広告のあり方についてお話しします。
世界と日本の広告史をたどる
広告の起源は、紀元前までさかのぼります。古代エジプトの壁画に描かれたお店の看板や、古代ローマの街角で見られる劇場の告知が、今の広告の原型といわれています。
15世紀に活版印刷術が発明されると、広告の世界は一変。文字や図版を大量に印刷できるようになり、チラシやポスターが街中にあふれるようになりました。
日本では、江戸時代の「引札(ひきふだ)」がこれに当たります。浮世絵師が描いた鮮やかなデザインの引札は、広告でありながら庶民の楽しみの一つでした。
時代が進み、ラジオやテレビが登場すると、広告は家庭の中にまで入り込みます。
そして今、インターネットやスマートフォンが普及し、広告は私たちの日常に欠かせない存在となりました。
日本の交通広告の歩み
日本の交通広告の歴史は古く、鉄道の発展とともに歩んできました。
明治時代の鉄道開業時から、駅や車内には広告が掲出され、人々の生活に溶け込むメディアとして定着しました。
日本の交通広告のはじまりは、明治5年に新橋―横浜間で日本最初の鉄道が開通してからわずか6年後の明治11年(1878年)に掲出された「乗り物酔い止め薬」の広告だったといわれています。
その後鉄道広告は一気に発達していき、明治18年ごろには中吊り広告の誕生とともに、車内広告も目覚ましい勢いで普及していきました。
明治36年(1903年)に路線バスの運行も始まり全国的に路線バスが普及していくのに合わせるように、大正14年(1925年)にはバス広告の車体広告も誕生しました。
日本の交通広告の始まりから150年近くたった今、交通広告は様々な形で私たちの目に飛び込んで来るようになりました。
ポスターや中吊り広告で「繰り返し目にしてもらう」という強みはそのままに、今ではデジタルサイネージや、スマートフォン広告と組み合わせる「メディアミックス」へと進化を続けています。
交通広告が持つ「古くて新しい」魅力
なぜ、今も交通広告が有効なのでしょうか?
その最大の理由は、「必ず視界に入る」という点にあります。
テレビやネット広告はスキップできますが、通勤電車の中吊り広告は、私たちが意識しなくても自然と目に入ってきます。この高い接触率こそが、交通広告の最大の魅力です。
さらに、交通広告は「信頼」を築く上でも大きな役割を果たします。
駅や電車という公共性の高い空間に広告を出すことで、「この会社は安心できる」という信頼感が自然と生まれます。
広告の未来をともに描く:最適な「想いの届け方」

現代の広告戦略に欠かせないのが、複数の媒体を組み合わせる「メディアミックス」です。
交通広告で幅広い層に認知を広げつつ、スマートフォンやSNS広告でターゲットを絞り込み、さらにウェブサイトへと誘導する。このように役割を分担することで、広告の効果は何倍にも高まります。
私たちは、交通広告に加えて、テレビ見逃し配信サービス(TVer)やニュースアプリ(スマートニュース)など、様々なデジタル広告の出稿をサポートしています。
特に、他社では難しい「お手頃な価格設定」でご提供しているのが強みです。
お客様の課題を深く理解し、広告を通じて最適なコミュニケーションをどう設計するか。それが私たちの使命です。
私たちは、「伝統を守りつつ、新しい挑戦を続ける」という姿勢を大切にしています。昭和23年(1948年)の創業以来長年の実績で培ったノウハウを基盤に、常に最適なご提案を心がけています。
広告の歴史を紐解きながら、未来の広告をどう描くか――ぜひ一緒に考えてみませんか。
広告戦略に関する相談はこちらから