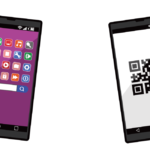2025年12月15日
その他広告が見つめてきた地域の変遷 ―60年の軌跡―

広告が地域を動かす力を、本気で意識し、行動に移し始めているのは、もはや大企業や自治体だけにとどまりません。小さなカフェ、デザイン事務所、美容室、専門職のフリーランスといった、地域で事業を営む個人事業主にとっても、広告は「お金をかけて派手に告知するもの」という従来の役割から、「地域と一緒に未来を共創するための共通ツール」へと、その本質的な定義を変化させています。
この変遷は、単なるマーケティング手法の進化ではなく、地域社会のあり方、経済活動の構造そのものを映し出しています。
本稿では、60年前、30年前、10年前、現在、そしてこれからという明確な時間軸を設定し、企業、自治体、そして個人事業主それぞれにとって、広告が地域開発とどのように複雑に結びつき、その風景を描き変えてきたのかを、多角的な視点から詳細に紐解いていきます。
目次
60年前:マス広告が作った「都市への憧れ」
およそ60年前、日本の社会全体が高度経済成長の渦中にあった時代は、テレビの急速な普及とともに、新聞、ラジオ、雑誌といった四大媒体によるマス広告が一気に力を持った、広告の黄金期です。
この時期、全国に流れる広告のメッセージとイメージの主役は、東京や大阪といった大都市圏の企業が提供する製品でした。冷蔵庫、テレビ、洗濯機といった「三種の神器」や、乗用車といった耐久消費財が中心であり、それらはまさに「豊かさ」と「近代化」の象徴でした。
当時のCMや新聞広告は、最新家電が並ぶ清潔なリビング、自家用車でのレジャー、高層ビル群が象徴する「豊かで便利な都市の生活」のイメージであふれていました。広告が地域開発に果たした役割は、非常に大きく、そして多義的でした。
第一に、広告は、都市の新しいライフスタイルへの強い憧れを全国津々浦々に創り出しました。広告が描く都市の豊かな生活イメージは、地方から都市への若年層の人口移動という社会現象と結びつき、その時代の空気感を象徴するものとなりました。
第二に、政府主導の工場立地や団地開発、高速道路網といった社会インフラ整備を後押しするイメージづくりを担いました。「より便利に、より効率的に」という発展の物語を広告が視覚的に補強したのです。
第三に、「全国一律」な品質と価格競争力を持つ製品の広告は、地方と都市の消費文化のギャップを埋め、均質な国民経済を形成する上で重要な役割を果たしました。
一方で、地方の商店や個人事業主が使える広告手段は、ごく限られていました。新聞の地方版の小さな広告枠、手書きのチラシ、店舗に掲げる看板やのぼり旗、そして商店街が共同で実施するセールチラシ程度でした。テレビCMはもちろん、新聞広告でさえ費用面で大きなハードルとなり、「広告=大資本のもの」という固定観念が強固に存在していました。
しかし、この小さな広告も、地域社会の景観形成に無意識に寄与していました。商店街の統一セールポスターのデザインや、街道沿いの個性的な看板は、結果としてその地域の「風景」や「ローカルな文化」をつくり、地域の印象を決める一要素になっていたのです。小さな広告活動が、意図せずとも地域の表情を形づくる重要な役割を担っていたと言えます。
30年前:地域ブランドの萌芽と「個性の時代」

30年前、1990年代半ばは、バブル経済の崩壊を経て、日本経済が「モノが売れる時代」から「選ばれる理由が必要な時代」へと大きく価値観を転換させた過渡期にあたります。消費者の視線が、単なる「機能」から「意味」や「体験」へと移行し始めたのです。
この変化に対応するように、自治体や第三セクターが主導する地域振興プロジェクトや、地方博覧会、大型地域イベントが全国的に増加しました。広告はこの時期、「地域そのものを売り出す」という、マス広告時代にはなかった新しいミッションを担い始めます。
自治体レベルでは、CI(コーポレート・アイデンティティ)の概念が導入され、ロゴマークやキャッチコピーを策定し、観光ポスターや誘致キャンペーンで全国に発信するという取り組みが活発化しました。また、地域の特産品を「○○ブランド」と名付けてデザインを統一したり、パッケージングを洗練させたりする、「地域ブランド化」の初期的な試みが多数見られました。
さらに、ローカル情報誌やフリーペーパーが各地で創刊され、地域の店やイベント、独自のライフスタイルを特集することで、「地元の魅力」を内側から再発見し、発信する役割を担いました。
企業側も、消費の多様化と地域ごとの市場性の違いを意識し、「地域密着」をキーワードに、チェーン店の出店やエリア限定キャンペーンを展開し始めます。全国展開のチェーンであっても、「このエリアだけの限定メニュー」や「地元の祭りとのコラボレーション企画」など、「ローカライゼーション」を強く意識した地域の色を前面に出す企画が増加しました。これは、地域住民に対する親近感の醸成と、個別の市場ニーズへの対応を目的としていました。
個人事業主にとっての広告の選択肢もわずかに広がります。地域情報誌への掲載、タウンページ広告、フリーペーパーへの出稿、商店街イベントとのタイアップなど、ローカル媒体の成長がその機会を提供しました。これにより、「地域の中で際立つ」だけでなく、「地域のらしさとセットで紹介される」という、新しい付加価値が生まれたのです。まだインターネットの存在感は小さく、広告は依然として紙媒体が中心でしたが、「地域の魅力を整理して伝え、個性化を図る」という意味で、現代につながる地域ブランドの萌芽がこの時代にあったと言えます。
10年前:SNSが広告を「個人のもの」に変えた

10年前、2010年代半ばには、スマートフォンがすでに広く普及しており、Facebook、Twitter(現X)、Instagram、YouTubeなどのソーシャルネットワーキングサービス(SNS)が日常生活のインフラとなった時代です。
この技術革新が、地域と広告の関係性を根本から変えました。
最大の変化は、「誰が発信者になれるか」という構造の転換です。それまで広告は、企業や行政の「資本力のある専売特許」のような側面が強かったのに対し、SNSの登場によって、情報発信の力が個人に劇的に分散しました。
具体的な影響としては、個人の投稿が瞬時に拡散し、観光地のイメージや地域の評判を左右するようになりました。飲食店の評価は、食べログやレビューサイトで詳細に可視化され、「口コミ」が「広告」を凌駕する力を持つようになったのです。また、小さな宿や個人店であっても、魅力的な写真とストーリーさえあれば、ハッシュタグを通じて世界中の人に見つけられるようになり、場所の制約を超えた集客が可能になりました。
同時期に、訪日外国人旅行者(インバウンド)が急増し、地方の観光地も海外からの視線を無視できなくなります。自治体や観光協会は、多言語のWebサイトや動画コンテンツを整備し、デジタルマーケティングと国際広報に投資を始めました。企業も、地方の魅力を活用した「地方×訪日客」向けの企画に積極的に投資を行い、地方創生とビジネス機会を結びつけようとしました。
この流れの中で、個人事業主にも大きなチャンスが訪れました。高価な機材がなくても、スマホだけで撮影した写真や動画がそのまま広告代わりになり、Instagramのハッシュタグやストーリーを駆使することで、地域の「映えるスポット」として認知を高められるようになりました。さらに、クラウドファンディングといった仕組みの普及は、地域の店づくりやイベント資金を、共感を集めるストーリーとともに集めることを可能にしました。
つまり、広告の主戦場は「お金をかけて枠を買う」という資本勝負から、「コンテンツとストーリーで共感を集める」という創造性勝負へと劇的にシフトしました。
企業はマス広告に加え、デジタル広告とSNS運用が必須となり、個人事業主にとっても、「顔が見える発信」や「ストーリーのある発信」といった信頼性の高い情報が、地域で選ばれる決定的な理由になっていきました。

現在:広告とまちづくりの融合、そして関係人口
そして現在。新型コロナウイルスのパンデミックとその後の数年を経て、「どこで働き、どこで暮らすか」という価値観は不可逆的に変化しました。ワーケーション、二拠点居住、リモートワークの定着といった新しい働き方の普及は、地域そのものを「働く場所」「暮らす場所」として見直す機会を生み出し、広告の役割もさらに重層的に変化しています。
今の広告は、単に「観光客を増やす」や「売上を上げる」という経済効果に留まらず、より長期的な地域社会の課題解決と結びついています。
具体的には、次の領域に深く踏み込んでいます。地域の空き家・空き店舗を活用したリノベーションプロジェクトの情報発信や、移住希望者に向けた仕事、暮らし、コミュニティをセットで提案する「ライフスタイル・コミュニケーション」、そして地域の小さなプレーヤーを束ねて見せる「エリア全体のブランド設計」です。
ここでは、広告と「まちづくり」の境界線が極めてあいまいになっています。例えば、ある商店街のイベント告知、自治体の移住プロモーション、そして企業の地域連携キャンペーンは、見る側からすればすべて「地域の未来図」を示す広告的メッセージとして認識されるからです。広告が、地域の住民や潜在的な移住者に対する「共感と参加の呼びかけ」としての機能を強めていると言えます。
企業にとっては、地域と連携したプロジェクトに取り組むことで、単に製品を売るだけでなく、「社会課題の解決に貢献する姿勢」を示し、ブランド価値を高める機会を得ています。また、社員の新しい働き方や学びの機会をつくり、新市場のテストベッドとして地域を活用するといった、多岐にわたるメリットを享受しています。
一方、個人事業主にとっては、単独で広告を打つよりも、「エリアの一員」としてまとまって発信することで存在感が増し、地域イベントやプロジェクトに参加することで、自身の店や事業のストーリーに奥行きと濃さが増します。
オンラインの情報発信(SNS、マップ、レビュー)と、リアルの場づくりを組み合わせることで、単なる顧客ではなく、「関係人口」や「ファン」を増やす効果が期待できます。いまや、広告は「一方的なお知らせ」ではなく、地域に関わるプレーヤー全員が共感し、行動するための「共通のストーリー」に近いものになってきています。
これから:AIと共創で「地域のインフラ」になる
これから先、広告は、データとAI、そして「共創」という二つの大きなキーワードによって、地域開発とさらに密接に結びついていきます。
まず、AIやデータ分析技術の進化によって、地域にどんな層の人が訪れ、どこを回り、何をきっかけに地域のファンになるのか、どの情報発信がどの層に最も届いているのか、そしてどんなコンテンツが「関係人口」「リピーター」「移住」といった実際の行動に繋がりやすいのか、といったことがこれまで以上に高い解像度で可視化されるようになります。
これにより、広告は単発のキャンペーンではなく、「地域の長期的なファン育成と、持続的な地域活性化を実現する仕組み」として、より戦略的に設計されていくでしょう。
企業にとっては、地域を舞台にしたプロジェクトを通じて、ブランドの世界観をリアルな場所で体験してもらい、SDGsや社会貢献とビジネスを両立させる取り組みが標準化します。
さらに、社員、顧客、地域住民を巻き込んだ共創の場をつくり出すことで、地域と共に成長する新しいビジネスモデルが確立されていきます。
そして、個人事業主にとっても、デジタル広告や情報発信のハードルは確実に下がっていきます。AIツールを使って、広告コピーやSNS投稿の魅力的な下書きを瞬時に生成できるようになり、オンライン予約や決済、顧客データといった小さな情報をもとに、地域に特化した効果的なキャンペーンを低コストで実施できるようになります。
また、地域のほかの事業者やクリエイターと連携し、エリア全体の「コンテンツ編集」に積極的に参加することで、地域全体の魅力向上に貢献できるようになります。
つまり、「広告のプロだけがつくる広告」から、「地域で暮らし働く人たちが自らデータを活用して組み立てる広告」へと進化します。広告は、道路や電気と同じように、「地域をつなぎ、動かし、未来をデザインする社会インフラ」として機能していくはずです。
結論:地域創りのための「共通言語」へ
企業にとって、地域はもはや単なる「販路のひとつ」ではなく、長期的な視点に立った「共に未来を創るパートナー」です。地域開発と広告の関係性を深く理解し、地域社会と持続的に関わることを前提としたコミュニケーション戦略を設計することが、これからの企業の競争力に直結します。
個人事業主にとって、広告は単に「費用対効果」の問題ではありません。自分の店や事業が「どんな地域の未来に貢献したいのか」、そのために「どんなストーリーを語り、誰と手を組むのか」を考えること自体が、すでに「地域開発に携わる広告活動」であり、自己の存在意義を高める活動になっています。
60年前には、広告は都市のショーウィンドウであり、地方との格差を示すものでした。30年前には、地域ブランドという個性化の看板を掲げ、10年前からは、誰もが世界に発信できるツールとなりました。そして今、そしてこれからは、地域の未来を一緒につくるための「共通言語」として、進化を続けています。
企業も、自治体も、個人事業主も、それぞれが自分の立場で、この「広告という共通言語」をいかに創造的に使いこなすかが、これからの地域の姿を大きく左右します。地域の価値は、ただ待っているだけでは決して育ちません。企業も、行政も、個人事業主も、それぞれの強みを積極的に持ち寄り、連携することで初めて、新しい市場や人の流れが生まれます。
いま、あなたの視点と行動を、地域創りに活かしてみませんか。地域での広告展開、交通広告とデジタル施策の組み合わせ、エリアマーケティングの戦略設計など、地域に根ざした広告のご相談は、お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。