2025年11月21日
未分類インバウンド集客はこう変わる! ――都市でも地方でも使える広告アイデア――
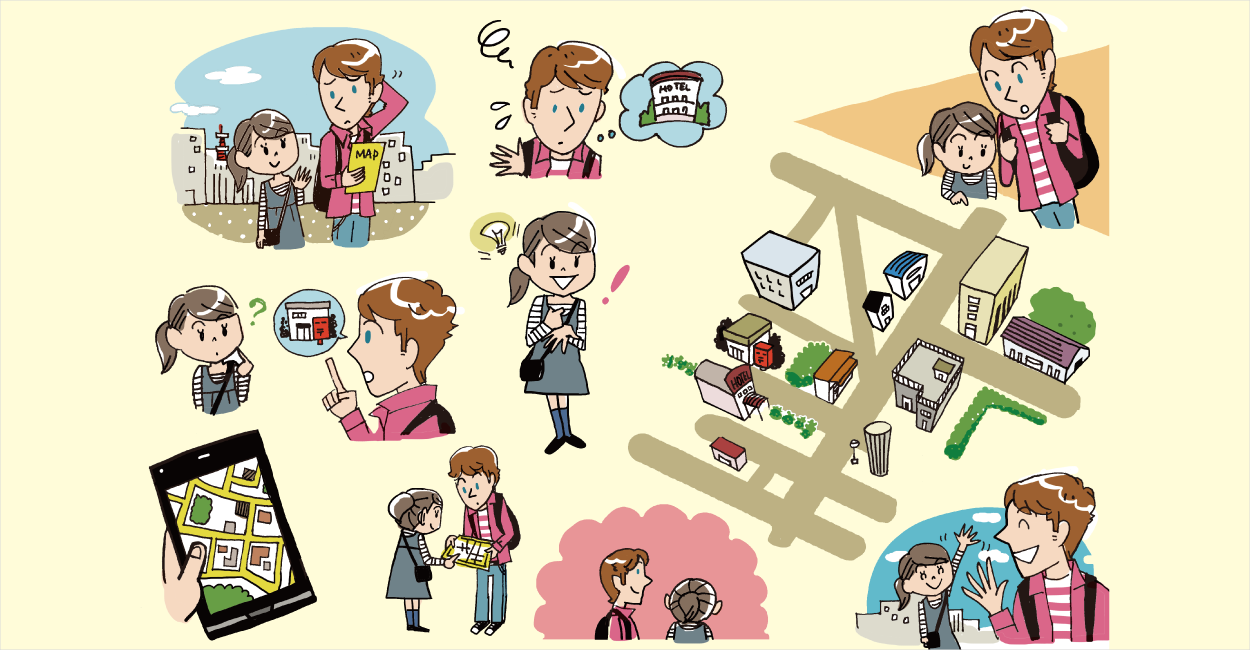
新型コロナウイルス感染症の影響で一時的に落ち込んだ訪日外国人観光客(インバウンド)市場は、2023年以降、驚異的なスピードで回復を遂げています。2025年上半期の累計訪問者数は過去最速で2,000万人を突破し、消費額も過去最高を記録するなど、この市場の成長はとどまるところを知りません。
この大きな波は、もはや一部の有名観光地や大企業のためだけのものではなく、都市の商業施設、地方の中小企業、そして個人事業主を含むすべての事業者にとって、具体的なビジネスチャンスとなっています。しかも、現代の旅行者は単に「物を買う」だけでなく、「特別な体験」を求めて、これまで注目されていなかった地方エリアにも足を伸ばすようになっています。集客の成功は、「現地に来てからどうするか」ではなく、「訪日前の情報収集段階でどう認知させるか」にかかっています。
この記事では、インバウンド市場の最新の変化を捉え、都市でも地方でも実践できる広告アイデアを、交通広告・サイネージ・動画・SNSを軸に、実践的なノウハウとデータを交えて深掘りしてご紹介します。
目次
インバウンド市場のパラダイムシフト
現在のインバウンド市場の成功は、単なる「数の回復」に留まらず、消費行動の質と地域の多様化という、戦略的に重要な3つの大きな変化に支えられています。
- ※【パラダイムシフト】
- これまでの常識や考え方、枠組みが大きく変わり、新しい基準や価値観に転換することを指します。ここでは「インバウンド集客の常識が変わった」という意味で用いています。
モノ消費からコト消費へ:消費行動の質の変化
かつての「爆買い」に代表される「モノ消費」(商品の大量購入)は落ち着き、現在は「コト消費」(体験やサービス)へと明らかにシフトしています。観光庁のデータでも、買い物代の比率が減少し、宿泊費や飲食費といった体験型の支出が増加していることが裏付けられています。旅行者は、地域文化の体験、地域住民との交流、温泉や食といった「特別な経験」により大きな価値を見出しており、広告戦略もこの体験価値の訴求にシフトする必要があります。
地方分散の本格化:SNSが後押しするニッチな旅
訪問先が、東京・大阪・京都・北海道といった定番地から、岩手、山口、鳥取といったこれまで外国人訪問者が少なかった地方エリアへと広がりを見せています。この背景には、SNSを通じて旅行者自身が発信するリアルでパーソナルな体験談が、次の旅行者を動かす強力な動機付けとなっていることがあります。ガイドブックには載らない「ローカルの魅力」を掘り起こし、発信することが、地方の事業者の集客における大きな鍵となります。
訪日前ターゲティングの重要性の増大
旅行者は、訪日前にSNSや動画サイトで徹底的に情報収集を行い、「他人が体験したことを自分も再現したい」「地元民のおすすめを知りたい」という傾向が非常に強いことが示されています。集客の勝負は「現地に来てから」ではなく、「訪日前の情報収集段階」で決まるようになりました。広告戦略には、現地での認知だけでなく、訪日前のデジタル空間でのターゲティング戦略が不可欠となります。
【戦術1】強制接触の価値:交通広告・サイネージの心理学

訪日外国人が滞在中に必ず利用する公共交通機関や駅構内での広告は、「移動中の時間」を最大限に活用する「強制接触メディア」であり、インバウンド集客において極めて重要な役割を果たします。
移動中の認知は「脳に残りやすい」
電車内や駅構内のサイネージは、目的地への移動中という、旅行者にとって最も関心が高く、情報に対して受容的になっている瞬間に接触できます。心理学のザイオンス効果(単純接触効果)の観点からも、移動中や待機中といった「隙間時間」に繰り返し目にする情報は、より深く記憶に定着しやすく、行動を強く促す効果があります。
交通広告を起点とした動線設計
交通広告は、単なる認知獲得に留まらず、行動へのシームレスな導線設計の起点となります。
- ・都市圏での事例
- 空港と都心を結ぶ電車内のサイネージで、入国直後の購買意欲が高い旅行者に免税店やドラッグストアを紹介します。
駅ナカ広告で最寄りの体験型アクティビティ(着物レンタル、和菓子作りなど)を、多言語の地図付きQRコードをセットで提示し、認知から行動へ直結させます。 - ・地方での事例
- 新幹線停車駅のサイネージで、温泉宿の露天風呂の映像や観光農園の収穫体験の様子を訴求し、地方滞在中の具体的な行動を促します。
地元の主要駅で、地元の工芸品や職人のストーリーを短尺動画で紹介し、「特別な一品」を手に入れるというコト消費的な価値を訴求します。
多言語字幕による「二重の波及効果」
サイネージや動画広告に、英語、中国語などの多言語字幕を付与することは、外国人観光客への理解度を高める効果に加えて、日本人消費者へのブランディング上の相乗効果が生まれます。日本人消費者にとって、多言語対応の広告は「外国人客も来る店=国際的に評価されている安心感と質の高さ」という印象を与え、国内客の利用促進にも繋がります。一つの広告枠で二つの市場に同時訴求できるこの手法は、コスト効率にも優れています。
【戦術2】「言葉を超える」力:動画とクロスメディア戦略
動画は、写真やテキストよりも強く「体験のイメージ」や「感情の動き」を、言語の壁を超えて瞬時に喚起できる、インバウンド集客における核心的なクリエイティブツールです。
動画クリエイティブの制作ノウハウ
動画制作においては、単なる商品紹介ではなく、感情や体験価値をダイレクトに訴求する映像表現が鍵となります。
【シズル感と没入感の訴求】
湯けむり立ちのぼる温泉、職人が包丁を研ぐ一瞬、抹茶を点てる繊細な所作といった映像は、見る人に「リラックス」「匠の技」「和の文化」といった感情を即時に伝えます。特に食や体験においては、五感を刺激するシズル感(食材や料理の新鮮さ、おいしそうに見える魅力)が行動を強く促します。
- ※【シズル感】
- 食べ物や飲み物などが、音や湯気、色、光沢といった視覚・聴覚的な表現によって、おいしそうだと感じさせる臨場感や魅力のことを指します。
【尺(長さ)と内容の使い分け】
- ・SNS用(5秒〜30秒)
- 瞬間的に興味を惹きつけ、シェアを誘発するキャッチーな要素を重視します。
- ・サイネージ用(15秒〜60秒ループ)
- 接触時間に合わせてメッセージを繰り返し認知させる、情報密度の高い構成を重視します。
成功事例に学ぶクロスメディアの構造
「おんせん県」「うどん県」といった成功事例の共通点は、地域固有の資源を「地域ブランド」に昇華し、複数の媒体で一貫したメッセージを伝えた点にあります。中小事業者でも、自店の特徴を印象的に伝える短尺動画を制作し、交通広告やサイネージで認知させつつ、SNSで詳細情報や予約導線を公開することで、この成功構造を小規模に実現できます。
認知から行動への動線設計の具体例
交通広告・サイネージ(認知) ⇒ QRコード/URL(行動の起点)⇒SNS/動画(興味・深掘り)⇒ 現地来店
【戦術3】訪日前のターゲティング:デジタル広告とSNS活用術
 インバウンド集客の勝敗は訪日前の情報収集段階で決まるため、デジタル広告とSNSを活用した精密なターゲティング戦略が不可欠です。
インバウンド集客の勝敗は訪日前の情報収集段階で決まるため、デジタル広告とSNSを活用した精密なターゲティング戦略が不可欠です。
【国・地域ごとの特性とプラットフォーム戦略】
ターゲット市場を明確に設定し、利用率の高いプラットフォームで広告を配信することが、予算効率を高めます。訪日外国人旅行者は、国・地域によって使用するSNSや消費行動が大きく異なります。
【中国市場】
- ・利用プラットフォーム
- Weibo、小紅書(RED)、WeChat
- ・広告戦略
- 購買力が高い層に向けて、KOL/KOCを活用した拡散とWeChat経由での予約・決済導線の確保が重要です。
【欧米豪市場】
- ・利用プラットフォーム
- Instagram、Facebook、Reddit
- ・広告戦略
- 長期滞在が多く、文化への関心が高いため、写真映えするビジュアルと、日本の歴史や文化背景を解説するコンテンツで訴求します。
【東南アジア市場】
- ・利用プラットフォーム
- Instagram、Facebook、TikTok
- ・広告戦略
- 短期旅行が中心でクーポンに敏感なため、短尺動画でのエンタメ性の高いコンテンツや、割引訴求が効果的です。
【SNS広告による精密なセグメンテーション】
SNS広告は少額から出稿可能であり、ターゲティングの精度が非常に高いことが最大の魅力です。
- ・精密なペルソナ設定
- 「来月日本へ旅行予定の台湾在住者で、日本の伝統工芸に興味がある20代〜30代女性」といった、極めて具体的なペルソナに対してのみ広告を配信できます。
- ・検証と改善の高速化
- 広告クリエイティブを複数パターン制作し、国や地域、年齢層別に効果測定を行うことで、常に最も効果の高いクリエイティブを運用し、検証と改善(PDCAサイクル)を高速で回すことが可能です。

【戦術4】ローカルとニッチの可能性:新しいインバウンド市場の開拓
インバウンド需要は多様化しており、既存の観光ルートや商材に留まらない、新しい市場の開拓が求められています。
飲食・土産以外に潜む意外な人気商材
外国人にとって「日本独自の文化」や「高品質な匠の技術」を体現する商材は、高い需要があります。
【日本の匠の技と文化】
- ・包丁・刃物
- 欧米圏の富裕層や料理人から、「一生もの」の高品質商品として評価されています。
- ・ハンコ(印鑑)
- 漢字文化の象徴として、自分だけのユニークな土産として需要が高いニッチ市場です。
【新しい分野への展開】
- ・美容・医療ツーリズム
- 高品質な日本の検診、エステ、美容サービスを目的とした富裕層の需要が拡大しています。
- ・アニメ・聖地巡礼
- 特定のローカルエリアがアニメの舞台となることで、集客力と消費単価が高いニッチな旅行者が集まります。
【ローカル集客の戦略的視点】
地方エリアは、大都市に比べて広告競合が少なく、広告が旅行者の目に留まりやすいという優位性があります。
- ・地域との連携強化
- 地域のDMOや観光協会と連携し、広域的な交通ルート情報と自社の広告を組み合わせることで、旅行者の利便性を高め、スムーズな訪問を促します。
- ・「リアルな日本」の訴求
- 大都市では得られない、地方ならではの温かい人情、伝統的な祭り、手付かずの自然といった「生活感」を動画で発信することで、地方訪問への強い動機付けとなります。
まとめとご提案:当社が担うインバウンド戦略の設計
インバウンド集客を成功させるためには、単なる「広告枠の購入」ではなく、市場の変化を捉え、リアルとデジタルを連携させた戦略全体の設計が必要です。
【成功のための戦略的チェックリスト】
広告戦略を成功に導くために、以下のポイントを常に念頭に置く必要があります。
- ・市場の明確化とターゲティング
- ターゲット国・地域の文化やSNS利用状況を詳細に分析し、メッセージを最適化します。
- ・体験価値中心のクリエイティブ
- 商品の機能だけでなく、「その場所でしか得られない特別な体験」を核とした動画や画像を制作します。
- ・多層的なアプローチの実施
- リアル広告(交通広告・サイネージ)で認知の絶対量を確保し、デジタル広告(SNS・動画)で興味を深掘りし、行動へ繋げる導線を構築します。
【当社が提供する伴走型サポート】
当社は、交通広告における長年の実績に加え、インバウンド集客に特化したサービスで、貴社のインバウンド戦略全体をサポートします。
- ・戦略設計とコンサルティング
- ターゲット国・地域の詳細な市場分析に基づき、最適な広告媒体と予算配分を提案します。
- ・多言語対応クリエイティブ制作
- 外国人目線での効果的な動画制作、多言語対応のランディングページ(LP)制作、SNS用コンテンツ制作を一貫して行います。
- ・デジタル広告運用と効果測定
- SNS広告、Web広告を国・地域別に精密に運用し、効果測定結果に基づいた継続的な改善(PDCA)を回します。
インバウンド市場は、都市の商業施設から地方の個人事業主に至るまで、すべての企業にとって成長の機会をもたらしています。当社は、単に広告の枠を売るのではなく、「外国人に伝えたい魅力がある」企業や店舗の価値を最大化し、集客から売上までの戦略全体を設計するパートナーとして、お客様を後押しします。
お問い合わせフォームやお電話から、いつでもお気軽にご連絡ください。





