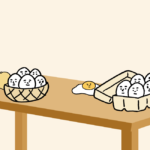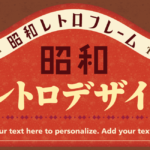2025年11月19日
その他医療広告と法律 ~厚生労働省ガイドラインに基づく適切な情報発信のために~
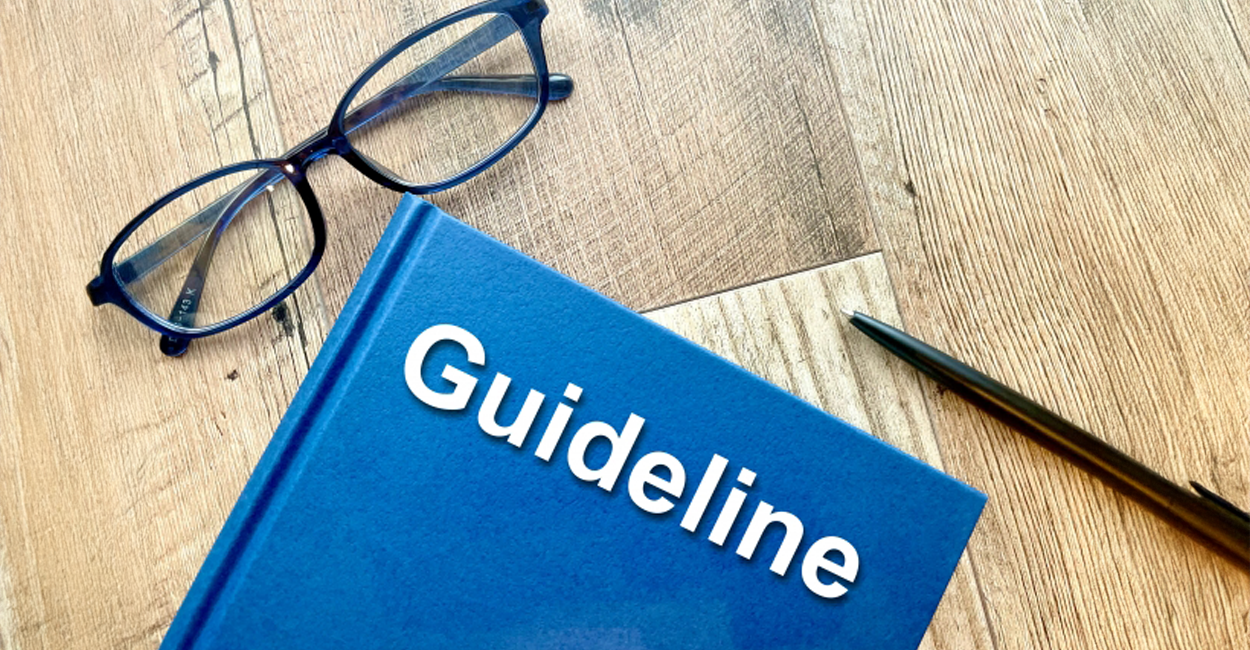
医療機関にとって「広告」は、患者に安心感を与え、治療やサービスを選ばれるきっかけとなる大切なツールです。しかし、他業種と異なり医療広告には厳格なルールが存在し、違反すれば行政指導や罰則の対象となる可能性があります。
厚生労働省は、医療機関が広告を行う際のルールをまとめた「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」(通称:医療広告ガイドライン)を策定しています。また、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師といった施術者についても、それぞれあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)や柔道整復師法に基づき「広告可能事項」が細かく定められています。
この記事では、医療機関や治療院が広告を出す際に特に注意すべき法律・ガイドラインについて、実例やよくある誤解を交えながら詳しくご紹介します。適切な情報発信を通じて、患者からの信頼を勝ち取るための戦略を解説します。
目次
1. 医療広告規制の基本的な枠組みと罰則
1-1. 医療法第6条の5による規制の大原則と禁止事項
医療広告は、「虚偽や誇大な表現を避け、患者に誤解を与えないこと」を大原則としています。この根拠となるのが、医療法(昭和23年法律第205号)第6条の5です。
特に禁止される広告(絶対的禁止事項) は、以下の通りです。
- 虚偽広告
- 「絶対安全な手術です」「どんな難しい手術でも必ず成功する」など、医学的にあり得ない内容や事実と異なる内容。
- 比較優良広告
- 「地域No.1」「最高の医療を提供」など、他の医療機関と比較して優良であることを示す表現。客観的な事実であっても、誤認を与えるおそれがあるため禁止されます。
- 誇大広告
- 事実を不当に誇張したり、誤認させたりする表現。「知事の許可を取得した病院です!」など、当然の義務を強調する表現も含まれます。
- 患者の体験談
- 患者の主観的な感想や治療後の満足度を掲載すること。口コミサイトからの転載も違反となります。
- 確実性の保証
- 「〇〇%の確率で治る」など、効果を断定・保証する表現。
- 治療前後の写真(ビフォーアフター)の原則禁止
- 個人差を無視して効果を保証するかのような誤解を与えるためです。(※例外規定は後述)
逆に、限定的に認められる広告は、診療科目、医師・歯科医師の氏名、診療時間、所在地など、患者の選択に資する客観的な事実に限られます。
1-2. 医療広告ガイドライン(2018年改正)の適用範囲拡大
2018年(平成30年)の医療法改正により、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」(医療広告ガイドライン)が定められ、ウェブサイトでの情報提供も規制の対象となりました。
このガイドラインは、広告の媒体や形式を問わず適用されます。
1-3. 違反時の行政指導と罰則
医療広告規制に違反した場合、以下の措置が取られる可能性があります。
- 行政指導
- まずは地方厚生局や都道府県による文書指導や口頭指導が行われます。
- 中止命令・改善命令
- 指導に従わない場合、広告の中止命令や内容の改善命令が出されます。
- 罰則
- 悪質な虚偽広告など、医療法第6条の5に違反し、改善命令にも従わなかった場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる場合があります。違反事例は公表されることもあり、医療機関の信用問題に直結します。

2. ホームページと広告物の境界線、そして「限定解除」
ウェブサイトは、医療機関にとって最も重要な情報発信ツールですが、その性質によって広告規制の対象となるかが決まります。
2-1. ホームページは「広告物」か?規制対象となる条件
医療機関のホームページは、原則として患者が自発的にアクセスして情報を得る媒体であり、すぐに「広告物」には該当しません。しかし、以下のような「誘引性」が認められた瞬間に規制対象となります。
- 広告物からの誘導
- 駅看板、チラシ、雑誌広告、インターネットのバナー広告などの「広告物」にホームページのURLやQRコードを掲載し、患者を誘導した場合。
この場合、ホームページの内容も広告規制の対象となり、禁止事項の掲載は許されません。
2-2. 症例写真(ビフォーアフター)を掲載するための「限定解除」
原則禁止されている症例写真(ビフォーアフター)については、患者の適切な受診に資するという観点から、例外的に以下の「限定解除の要件」を全て満たした場合に限り、ウェブサイト等への掲載が認められます。
・自由診療に関する情報であること。
・治療内容、費用、主なリスク・副作用の詳細を明確に記載すること。
・未成年者(18歳未満)の術前術後の写真は掲載しないこと。
・「患者さんの状態により効果には個人差がある」旨を明記するなど、誤認防止のための注意書きを付記すること。
これらの要件を満たすためには、単に写真を載せるだけでなく、写真と同等以上に詳細な情報(文章)を併記する必要があり、適切なリスク表示が不可欠です。
2-3. よくあるウェブサイトの落とし穴
- データの根拠不明示
- 「患者満足度99%」などと記載しながら、その調査方法や根拠となるデータをホームページ上で明確に示していない場合、虚偽広告や誇大広告とみなされます。
- 不適切な専門医の表記
- 「厚生労働省が認可した○○専門医」という表現は、専門医の資格認定は学会が実施するため虚偽広告にあたります。
- 雑誌記事の引用
- 過去に雑誌や新聞で紹介された記事を、あたかも自院の優位性の根拠であるかのように引用・掲載することは禁止されています。
3. 自由診療と広告表現の深掘り
3-1. 自由診療(保険外診療)における費用明示の義務
自由診療に関する広告では、医療法に基づき、費用に関する曖昧な表現は避けなければなりません。
- 総額の不明確さの禁止
- 「二重整形 ○万円~」といった表示だけでは不十分です。この費用が最低料金なのか、標準的な料金なのかを明記し、別途必要となる初診料、麻酔代、検査費用などの詳細も併記する必要があります。
- 不当な価格訴求の禁止
- 自由診療は景品表示法にも抵触しやすいため、「期間限定」「特別価格」などを過度に強調し、患者を不当に誘引する表現は、品の低下につながるとして禁止されています。
3-2. 治療効果の断定とリスク・副作用の記載
自由診療は多様な治療法が存在しますが、その効果を断定する表現(「必ず効果がある」)は禁止です。また、限定解除の要件にもある通り、メリットだけでなく、治療に伴う主なリスクや副作用を、メリットと同程度に分かりやすい場所・大きさで記載しなければなりません。
4. あはき・柔整の広告規制と法律
4-1. 広告可能事項の限定(あはき法・柔道整復師法)
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)、柔道整復師は柔道整復師法に基づき、広告できる事項が厳しく限定されています。
広告可能事項:施術所名、住所、電話番号、営業時間、施術者の氏名および資格のほか、予約制であること、出張による施術を行う旨など。
これらの資格者の広告は、医療機関の広告よりもさらに規制が厳しく、例えば「肩こり専門」「腰痛が治る」といった具体的な症状や効果を謳うことはできません。
4-2. 規制を回避するための情報発信
規制対象となるのは「患者を誘引する目的」を持つ広告です。したがって、以下の媒体での情報発信は、規制の対象外とみなされる場合がありますが、ここでも体験談や虚偽表示は避けなければなりません。
・院内掲示・院内で配布するパンフレット
・患者等が自主的に掲載する体験談(施術所側が費用を負担したり、掲載を依頼したりした場合は広告とみなされます)
・学術論文、学術発表等

5. 医療広告で特に注意すべき関連法規の具体的な違反事例
医療機関の広告が抵触する可能性のある主要な関連法規には、景品表示法と薬機法があります。
5-1. 景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)との関係
景品表示法は、一般消費者の自主的・合理的な選択を阻害する不当な表示を禁止する法律です。
- 違反事例(優良誤認表示)
- 科学的な裏付けがないにも関わらず、「飲むだけで12kg痩せる」「当院独自の治療法でアトピーが完治する」などと、実際よりも著しく優れていると誤認させる表示。
- 違反事例(有利誤認表示)
- 「今だけ半額」と謳っているが、実際には常にその価格で販売されており、お得であるかのように偽っている表示。
自由診療やサプリメント、美容機器などの販売に関わる広告は、特に景品表示法の規制対象となりやすく、消費者庁による措置命令や、悪質な場合は課徴金納付命令が出される可能性があります。
5-2. 薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)との関係
薬機法は、医薬品や医療機器の効能効果の誇大広告を規制する法律です。
- 違反事例
- 医療機関が提供する健康食品や化粧品について、「癌が治る」「血糖値が下がる」など、医薬品的な効能効果を謳う表示。これらは、無承認の医薬品の広告とみなされ、薬機法違反となります。
- 医療機器の効能
- 承認されていない医療機器の効能(例:特定の症状が治る)を表示することも禁止です。
医療機関であっても、広告内容が薬機法の規制に抵触しないよう、販売・提供する商品やサービスの効能効果には細心の注意を払う必要があります。
6. 患者に伝えるべき情報と信頼を獲得する表現の工夫
医療広告は制約が多い一方で、患者にとって必要な情報を正しく伝える責任があります。制約が多いからこそ、情報発信の「質」が重要になります。
6-1. 誇張を避けた「誠実な情報」の発信
患者は「何ができるか」「どのくらい費用がかかるか」「信頼できるか」を知りたいのです。客観的事実に基づいた誠実な情報発信が、結果として信頼につながります。
- 医師の経歴・専門性
- 認定資格や所属学会名を正確に記載します(例:「日本整形外科学会 認定整形外科専門医」)。
- 料金体系
- 自由診療は特に、総額や別途費用を含めた明確な料金シミュレーションを提示し、患者が安心して検討できるようにします。
- 設備の紹介
- 最新機器の導入事実を記載する際は、その機器が何の目的で使用されるかという客観的な情報に留め、効果を過度に誇張しないようにします。
6-2. 表現の工夫と「第三者の目線」の活用
直接的な効果訴求ができない代わりに、患者に安心感を与えるための表現を工夫します。
- コミュニケーションの姿勢
- 「患者さまに寄り添い、丁寧に説明します」「不安を解消するため、無料のカウンセリングも実施しています」など、サービスの質や安心感に繋がる姿勢を伝えます。
- 写真利用の限定
- 治療効果を示すビフォーアフター写真ではなく、施設の外観や内装、清潔感、スタッフの笑顔など、安全と信頼性に繋がる情報に限定します。
- 第三者チェック
- 広告を作成する際は、必ず医療法や関連法規に詳しい専門家(弁護士、広告代理店)のチェックを受ける体制を構築することが、違反リスクを最小限に抑える最善の方法です。
まとめ
医療広告は、一般的な商業広告に比べて医療法をはじめとする複数の法律によって厳しい制限があります。
- 医療法
- 虚偽・誇大・体験談・比較優良・確実性保証は厳禁。ウェブサイトも誘導があれば規制対象となる。
- 自由診療
- 費用を明確に表示し、リスク・副作用を併記することで、症例写真等の限定解除が可能となる。
- あはき
- 柔整:あはき法、柔道整復師法に基づき、広告可能事項が厳しく限定されている。
- 関連法規
- 不当表示や過度な割引は景品表示法、医薬品的な効能効果の訴求は薬機法に抵触するリスクがある。
一見すると「縛りが多い」と感じるかもしれませんが、ルールを守りつつ誠実な広告を行うことは、結果として患者からの信頼につながり、長期的な集患にも効果的です。
当社は、交通広告・デジタル広告を中心に、医療機関の広告運用もサポートしてまいりました。法律を遵守しながら効果的に情報発信するためのご相談も承ります。
お気軽に、お電話またはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。