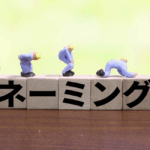2025年10月29日
その他小さな会社こそ取り組むべき「仕組み」としてのマーケティング

広告や営業活動の成果が安定しないことに悩んでいる中小企業の担当者は多いのではないでしょうか。
「広告を打っても一時的に反応があるだけ」「営業で必死に動いても成約につながらない」といった経験はありませんか?
成果を安定させる鍵は、広告や施策の量を増やすことではなく、マーケティングを仕組みとして設計することにあります。仕組み化されたマーケティングは、単発のキャンペーンや広告に依存せず、中長期的に安定した集客と信頼の構築を可能にします。
本記事では、中小企業でも実践できるマーケティングの仕組みづくりの考え方と具体策を、実例を交えて紹介します。
目次
成果が安定しない中小企業のマーケ課題
波のある集客・売上の実態
多くの中小企業では、単発の広告や営業活動に依存しているため、集客や売上に波が出やすくなります。
広告やSNS施策は一時的に成果を出すことはできますが、止めた瞬間に集客がゼロになってしまうことも少なくありません。例えば、キャンペーン実施期間中は問い合わせが急増するが、施策が終わると翌月はほとんど反応がない、といった状況です。
このような波は、営業やマーケティング担当者のモチベーション低下にもつながります。
リソースの限界
小規模な企業では人員が限られており、営業とマーケティングを兼務することも珍しくありません。少人数でマーケティングを担当している企業では、施策を続ける時間や知識が限られています。そのため、戦略的に施策を組み立てる余裕がなく、場当たり的な運用になりがちです。
さらに、マーケティングの効果を分析して改善する時間も不足しており、成功体験を積み重ねることが難しくなります。
マーケティングを「仕組み」として捉える
広告やキャンペーンは「点」の施策
広告や単発キャンペーンは、瞬間的な反応や成果を生みますが、継続的な集客にはつながりません。あくまで「点」として位置づけることが重要です。
例えば、チラシやSNS広告を一度出しただけでは、十分に認知され信頼を獲得する効果は見込めません。
マーケティングは「線の戦略」
一方でマーケティング活動は、【認知】 → 【興味】 → 【信頼】 → 【購買】という流れを設計する「線の戦略」です。
認知:
まず自社やサービスを知ってもらう
興味:
具体的な課題や解決策に関心を持ってもらう
信頼:
実績や事例で信頼を積み上げる
購買:
購買行動を自然に促す導線を作る
この線をつなげることで、短期的な広告やキャンペーンなどの施策の実施がない期間でも成果が途切れない仕組みを作ることができます。
仕組み化のメリット
マーケティングを仕組み化すると、次のような効果があります。
施策の効率化:
一度作った仕組みを再利用し、繰り返し使うことができる
成果の再現性:
誰が担当しても一定の効果を出すことができる
集客・信頼構築の継続性:
広告やキャンペーンに依存せずに成果が持続する

中小企業で実践できる仕組み化のステップ
仕組み化するといっても、何から手をつければよいか悩む方も多いことでしょう。特に、リソースの少ない企業の場合、最初から一気に全てに取り組もうとすると、回らなくなり、仕組み化が失敗に終わります。焦らず、以下のステップで、順に進めて行きましょう。
ステップ1|認知づくり
まず最初は、自社やサービスを知ってもらい、「認知」を高める段階です。知名度のない会社がいきなり、TVや新聞などのマス広告を出したとしても、あまり効果はありません。広告費も高額なため、小さい会社には無理があります。小規模でも取り組みやすい施策から始めましょう。
自社ブログ・コラム:
自社の商品・サービスが関係する分野の課題解決やノウハウを発信。
SNS発信:
少人数でも週1〜2回の定期投稿を意識。カジュアルな投稿も効果的。
メルマガ配信:
既存顧客や問い合わせリスト向けに、キャンペーンの案内などを発信。
これ以外に、低価格で長期間掲出できる広告(駅構内ポスター、交通広告、地域密着型の看板など)も、認知づくりの仕組みに組み込むことが可能です。
これらは一度出稿すれば継続的に目に触れるため、SNSやブログと同様に「潜在層への長期的な接点づくり」として機能します。
例えば、月額数万円で掲出できるローカル交通広告を半年以上継続すると、「見たことがある」「気になっていた」という反応が自然に増え、後から配信するメルマガやWeb広告の反応率が上がるなどの効果につながります。
(参照:「知られる企業」になるためのマーケティングの基本―認知づくりを仕組み化する3つのポイント)
ステップ2|信頼づくり
残念ながら、見込み客に「認知」されただけでは、まだ購入にはつながりません。「信頼」を積み上げる取り組みが重要です。会社や商品・サービスについて、より具体的で役立つ情報を発信するなどの活動を行います。
顧客の声・導入事例の公開:
成功事例や改善効果を具体的に示す。
問題解決型コンテンツの提供:
読者の具体的な課題に寄り添った情報、専門的な情報を発信する。
継続的な情報提供:
メールやニュースレターで関係性を維持する。
<参照>:
信頼が企業価値を高める ― BtoBマーケティングにおける「信頼づくり」の仕組み化
「選ばれる会社」になるためのマーケティング ― 信頼づくりを仕組み化するポイント
ステップ3|関係づくり
次は、「信頼」を構築することができた見込み客との「関係」を育てるステップです。信頼を得たステップ2の段階では、まだ購入を迷っている人もいるでしょう。その場合、身近に感じてもらえるような、より丁寧なコミュニケーションが大切です。
あるいは「購入」してもらえたとしても、お客様を放置してしまったら、再度の購入には繋がりません。ファンになってもらい、継続的な購入や友人への紹介などをしてもらえるような「関係」づくりに取り組みましょう。
定期発信:
メルマガやLINE公式アカウントで継続的に、新商品や商品の使い方などの情報を届ける。
オンラインセミナーや体験会:
直接関わり、より具体的な課題に寄り添うことで、見込み客・顧客との距離を縮める。
小さなフォロー:
電話やメールで丁寧に確認・相談に応じる。
仕組みに組み込む広告の考え方
広告も必ずしも全てが短期的な施策ではありません。目的と期間によって適切な媒体を選ぶことで、マーケティングの「仕組み」に組み込むことができます。
短期的な広告(SNS広告・キャンペーン)
新商品やイベント告知など、短期的な集客に活用
長期的な広告(交通広告・看板・業界誌掲載)
継続的な認知形成やブランド想起の一部として、マーケティングの仕組みに組み込み可能
後者の交通広告や看板などはOOH(Out of Home)広告と呼ばれ、単に見てもらって認知を高めるだけではなく、ブログやSNS発信などの「線」の施策と組み合わせることで、「見たことがある」→「調べてみよう」→「問い合わせ」という自然な流れを生み出すことにつながります。検索からWebサイトに誘導したり、広告自体がSNSで拡散されたりなどの連携も可能です。
(参照:“売って終わり”にしない ― 顧客との関係を育てる仕組み化マーケティング)

成功事例から学ぶ仕組み化の効果
事例1|営業の手間を減らして成約率アップ(BtoB企業)
背景
あるBtoB企業では、営業担当者1人あたりの新規顧客開拓の負荷が非常に高く、問い合わせ対応に追われていました。単発の展示会参加や電話営業に偏った施策では、成約率が安定せず、営業担当者の負担が増す一方でした。
導入した仕組み
1.メールマーケティングの自動化
・問い合わせリストや展示会参加者リストを課題別にセグメント
・週1回の自動配信で、営業が手をかけずに関係性を維持
<ポイント>
一度に大量配信せず、セグメントごとにメールの内容をパーソナライズすることで反応率を高める
2.導入事例・顧客の声の体系化
・成功事例を業界別・課題別に整理
・メールや資料で事前に配布し、営業が説明する時間を短縮
<ポイント>
抽象的すぎる事例は説得力が低下するため、数値やビフォーアフターなどを必ず入れる
3.オンラインセミナーの定期開催
・月1回のWebセミナーで共通課題を解説
・セミナー後のフォローも自動化し、見込み客の関心を維持
成果
・営業担当者1人あたりの対応負荷が半減
・成約率が従来の1.8倍に向上
・展示会や電話営業だけでは得られなかった高品質なリードの獲得に成功
事例2|施策をやめても集客が止まらない(BtoC企業)
背景
あるBtoC企業では、SNS投稿や広告に依存して集客を行っていました。しかし、広告予算や投稿頻度にムラがあり、問い合わせ数が安定しませんでした。また、SNS広告だけでは信頼構築が十分に行えず、商談化率も低下していました。
導入した仕組み
1.ブログ・コラムの定期更新
・読者の課題に沿った情報を週1回発信
・SEO対策を施し、検索経由の安定した流入を確保
<ポイント>
記事が長すぎたり専門用語ばかりでは読まれないため、分かりやすく構成
2.顧客レビュー・体験談の発信
・購入者の体験談や改善事例を記事・SNSで公開
・数値やビフォーアフターを明確に示すことで信頼度アップ
<ポイント>
感想だけで抽象的な体験談では説得力が低下するため、具体性を持たせる
3.ナーチャリング(リード育成)施策の構築
・メルマガやLINE公式で定期配信
・キャンペーン情報だけでなく、課題解決型コンテンツも組み込む
<ポイント>
単発配信ではなく、シリーズ化することで信頼が積み上がる
4.広告は補助的に活用
・新サービスやイベントの告知時にのみ、少額で広告を使用
・集客の安定化よりは「点の補強」として活用
成果
・広告施策を一時停止しても、月間の問い合わせ数はほぼ変動なし
・SEOやナーチャリング施策により、広告費を抑えつつ安定した集客を実現
・顧客からの問い合わせの質が向上し、商談化率もアップ
仕組み化で「集客の偶然」を「再現可能な成果」に変える
中小企業のマーケティング成功の鍵は、一度きりの成功を再現できる仕組みを持つことです。継続的な顧客接点・認知づくり・データ活用を組み合わせることで、「集客がうまくいく時とそうでない時の差」をなくすことができます。
仕組み化は、マーケティングを「担当者の勘と経験」から「企業の資産」に変えるプロセスです。小さく始めて、少しずつ仕組みを整えることが、最も確実な第一歩です。