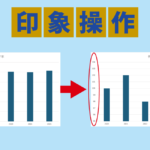2025年10月30日
交通・屋外広告バス広告に隠された物語 ―「みんなの乗り物」が広告メディアになるまで―

バスに乗るという行為は、私たちの日常に深く根付いています。
通勤・通学、買い物、旅行…バスは、ただ目的地に連れて行ってくれるだけの乗り物ではありません。
車窓から見える景色、停留所で乗り降りする人々の表情、そして車内に流れるアナウンス。
バスは、その地域に暮らす人々の息遣いを伝える、「走る文化」そのものです。
この記事では、そんなバスにまつわる意外な小ネタやトリビアを交えながら、バスがなぜ広告メディアとして強い力を持つのか、その理由をひも解いていきます。
目次
バスはなぜ「みんなの乗り物」になったのか?
バスのルーツは、17世紀のフランス・パリにさかのぼります。
1662年、数学者で哲学者のパスカルが考案した「乗合馬車」が、市内を初めて走りました。
この馬車には、「すべての人々のための」という意味を持つラテン語の「オムニブス(omnibus)」という愛称がつけられ、これが「バス」という言葉の語源になったと言われています。
つまり、バスは誕生したその時から、「ごく一部の富裕層のため」ではなく、「すべての人々のため」という公共性を宿していました。この精神は100年以上経った今も受け継がれ、バスが「誰もが日常的に接触できる」広告メディアであることの原点となっています。
「日本初」をめぐる京都と広島の物語
日本のバスの歴史には、少し面白いトリビアがあります。
1903年9月20日、京都の二井商会が祇園〜七条~堀川中立売間で、輸入車を使った乗合自動車を走らせました。これが、一般的に「日本初のバス」とされています。
一方で、広島でもバスの歴史が動いていました。1905年、横川〜可部間で国産車を使った路線が登場したのです。
この「日本初」をめぐる論争は、「輸入車を使った営業運行が先の京都」か、「国産車第一号の広島」か、という定義の違いから生まれました。結果として、京都の運行開始日である9月20日が「バスの日」と制定され、今も全国各地で記念行事が行われています。バス広告の世界では、この「バスの日」に合わせてキャンペーンを展開するなど、「歴史」を活かした広告が数多く生まれています。
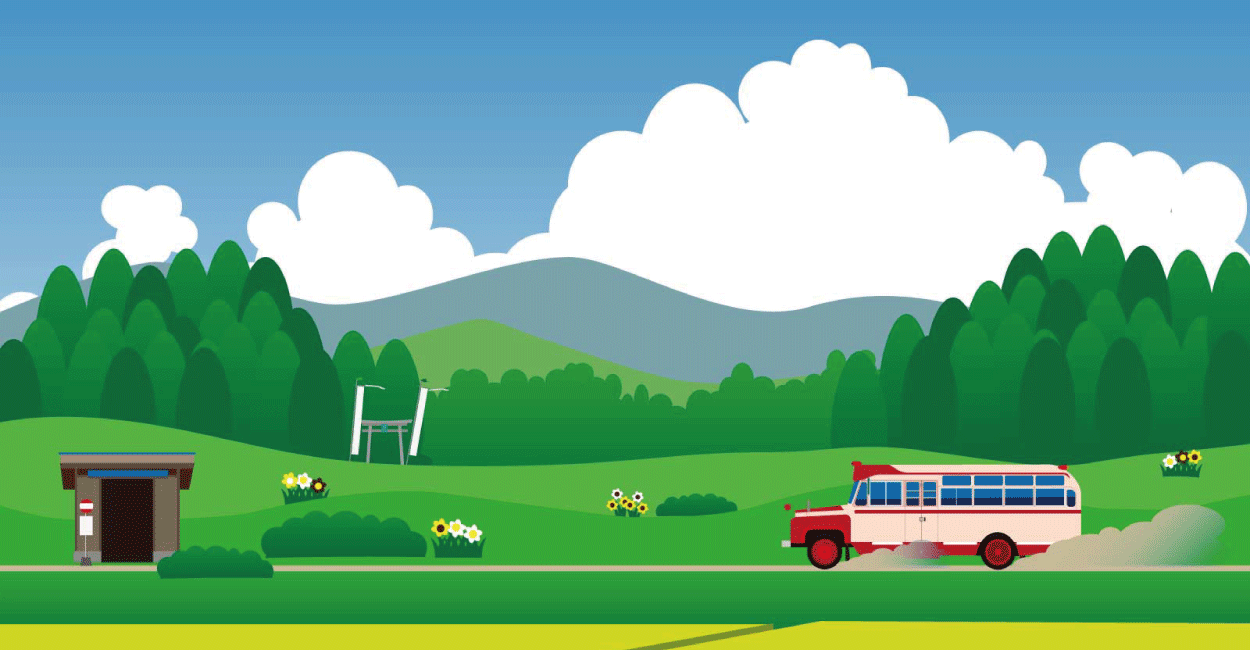
降車ボタンは日本独自の文化
バス車内で聞く「ピンポーン」という音。私たち日本人には当たり前のこの「降車ボタン」は、実は日本独自の文化だということをご存知でしょうか?
海外の多くの国では、路線バスが停留所ごとに必ず停まる運行形態が一般的で、乗客が降車を知らせる仕組みはあまり使われていません。
日本で降車ボタンが普及したのは、効率性とサービス性を両立させるためでした。乗客が降りたい場所を知らせることで、無駄な停車時間をなくし、スムーズな運行を実現したのです。
広告的に見ると、この「押す」という行為は、日本のバス文化そのもの。そして、バス広告は、この「体験」の中に自然と溶け込むことができます。座席の真ん前にある広告を眺めながら、思わず降車ボタンに手が伸びる。そんな「生活に根差した行動」の中に、バス広告は存在しているのです。
バス広告の「強み」を紐解く3つの小ネタ
バスが単なる乗り物ではなく、広告メディアとして大きな力を持つのは、そのユニークな特性があるからです。
1.「最長」バス路線が示す、移動時間の価値
奈良交通が運行する「八木新宮線」は、約169kmを6時間半かけて走破する、日本一長い路線バスです。
この路線が示しているのは、バスが持つ「移動時間の長さ」という価値。
私たちは、バスに乗っている間、スマートフォンを操作したり、外の景色を眺めたり、ぼんやりと考え事をしたりします。この限られた空間と時間は、広告主にとって、乗客にメッセージを届けるための貴重な機会となります。
2.「シートベルトがない」バス広告の意外な利点
路線バスには、シートベルトが基本的にありません。これは、「立ち乗りを前提とした設計」が法律で認められているためです。
広告の観点から見ると、これは大きなメリットとなります。なぜなら、座席に座っている人だけでなく、立っている多くの人にも広告が届くからです。窓や手すり、天井など、乗客の目線が自然と向かう場所に広告を掲出することで、より多くの人々に情報を届けることができます。
3.「バスターミナル」が持つ、新しい広告の接点
近年、新宿の「バスタ新宿」をはじめ、全国各地でバスターミナルの再開発が進んでいます。
バスターミナルは、出発前の待ち時間や、到着後の回遊で、多くの人々が必ず「滞留」する場所です。
・高い視認性:サインボードやデジタルサイネージで、多くの人に広告を見てもらえる。
・多様なターゲット:ビジネスマン、旅行者、地元住民など、幅広い層にリーチできる。
このように、バスターミナルは、バスの車内広告とは異なる、新しい広告の接点として価値を高めています。
バスは地域を映し出すメディア
バスにまつわる小ネタを知れば知るほど、バスが単なる公共交通機関ではなく、地域の文化や歴史を背負ったメディアであることが見えてきます。
京都と広島の「日本初」論争が示すように、バスは地域の個性を育んできた。
降車ボタンが象徴するように、バスは生活の一部として定着している。
最長路線やバスターミナルが示すように、バスは人々の生活動線を網羅している。
バス広告は、そんなバスという媒体の特性を活かし、地域の文化や暮らしに寄り添うようにメッセージを届けます。
もし、あなたのビジネスを、地域の人々に、そして観光で訪れた人々に、「バスという日常」の中で伝えたいとお考えなら、ぜひ私たちにご相談ください。あなたの街に最適なバス広告のプランをご提案します。
地域に根ざしたバス広告の相談はこちらから