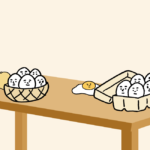2026年2月5日
マーケティング広告はなぜ0と1では割り切れないのか 量子論的視点で考える広告効果の揺らぎ
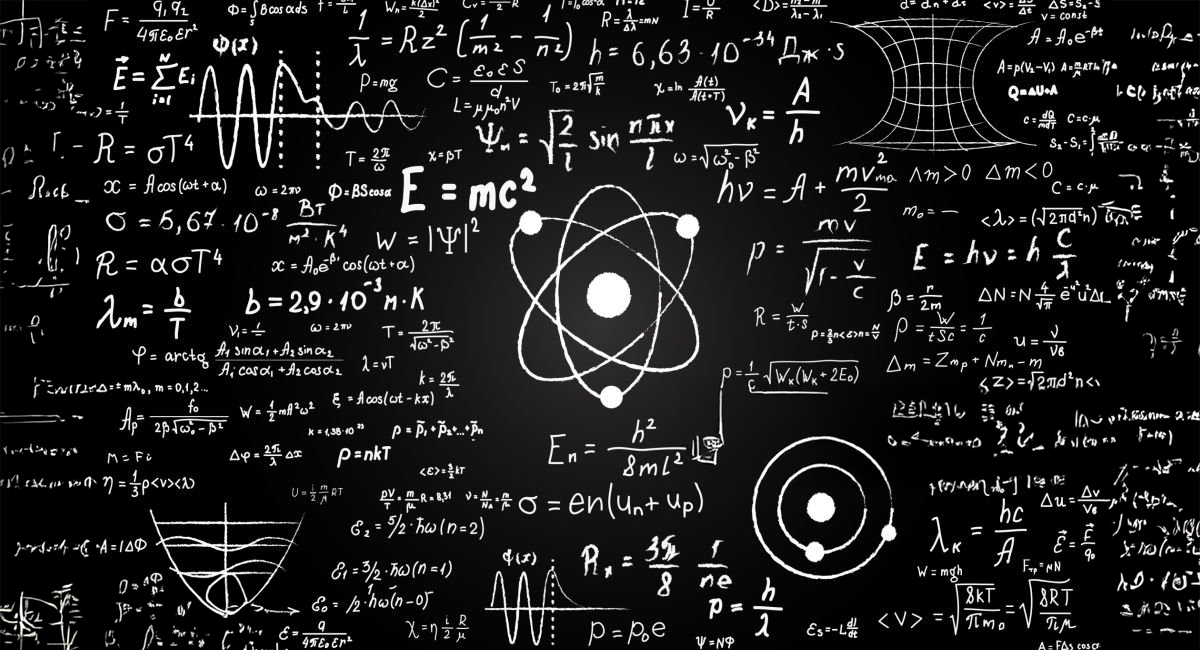
以前のコラム「1byteの決断」では、わずか8つの選択から256通りもの答えが生まれるという話をしました。
コンピュータの世界では、すべてが0か1かという二択の積み重ねで成り立っています。オンかオフか。YesかNoか。その単純な判断を8回重ねるだけで、256という多様な結果にたどり着く。この発想を借りれば、広告の意思決定もシンプルに整理できるのではないか、というのが前回の趣旨でした。
しかし、現実の広告は、そこまで素直ではありません。
同じ条件で設計したはずなのに、結果が安定しないことがあります。数値上は改善しているはずなのに、現場では手応えを感じられないこともあります。逆に、理屈では説明できないのに、人の記憶に強く残る広告が生まれることもあります。0と1で設計しているはずなのに、結果は0と1では割り切れない。この違和感は、広告に携わる多くの人が、どこかで感じているものではないでしょうか。
なぜ、広告は設計どおりにいかないのか。なぜ、同じ広告でも届き方が変わるのか。この問いに向き合うとき、ひとつの補助線として役に立つのが、量子論という考え方です。量子論は、ミクロの世界を扱う物理学の理論ですが、その根底にある発想は、私たちが普段抱いている常識を揺さぶるものです。世界は最初から確定しているわけではない。観測されて初めて、ひとつの状態に定まる。この視点を借りると、広告の揺らぎが少し違って見えてきます。
ここでは、量子論の考え方を手がかりに、広告がなぜ割り切れないのかを掘り下げていきます。
広告を「0か1か」で語りたくなる理由
広告の世界では、成果を数値で語ることが当たり前になっています。
クリック率、コンバージョン率、リーチ数、フリークエンシー。こうした指標は、広告の効果を客観的に測るための道具として広く使われています。数値があれば、成功と失敗の線引きがしやすくなります。改善の方向性も見えやすくなります。判断に迷ったとき、数値は頼れる拠り所になります。
数値化がもたらす安心感
数値で語れるということは、説明ができるということです。
なぜこの媒体を選んだのか。なぜこの予算配分にしたのか。なぜこのタイミングで配信したのか。すべてに数字の裏付けがあれば、社内の合意も取りやすくなりますし、上司や経営層への報告もスムーズになります。広告は投資です。投資である以上、成果を数値で示すことは当然のことですし、そうでなければ予算を確保し続けることも難しくなります。
デジタル広告の普及によって、この傾向はさらに強まりました。インターネット上の広告は、誰が見たか、何回見たか、どこをクリックしたか、その後どんな行動を取ったかまで追跡できます。テレビCMや新聞広告の時代には見えなかったものが、見えるようになりました。見えるようになったことで、広告は科学的に管理できるものだという認識が広がりました。
正しく設計すれば正しい結果が出るという前提
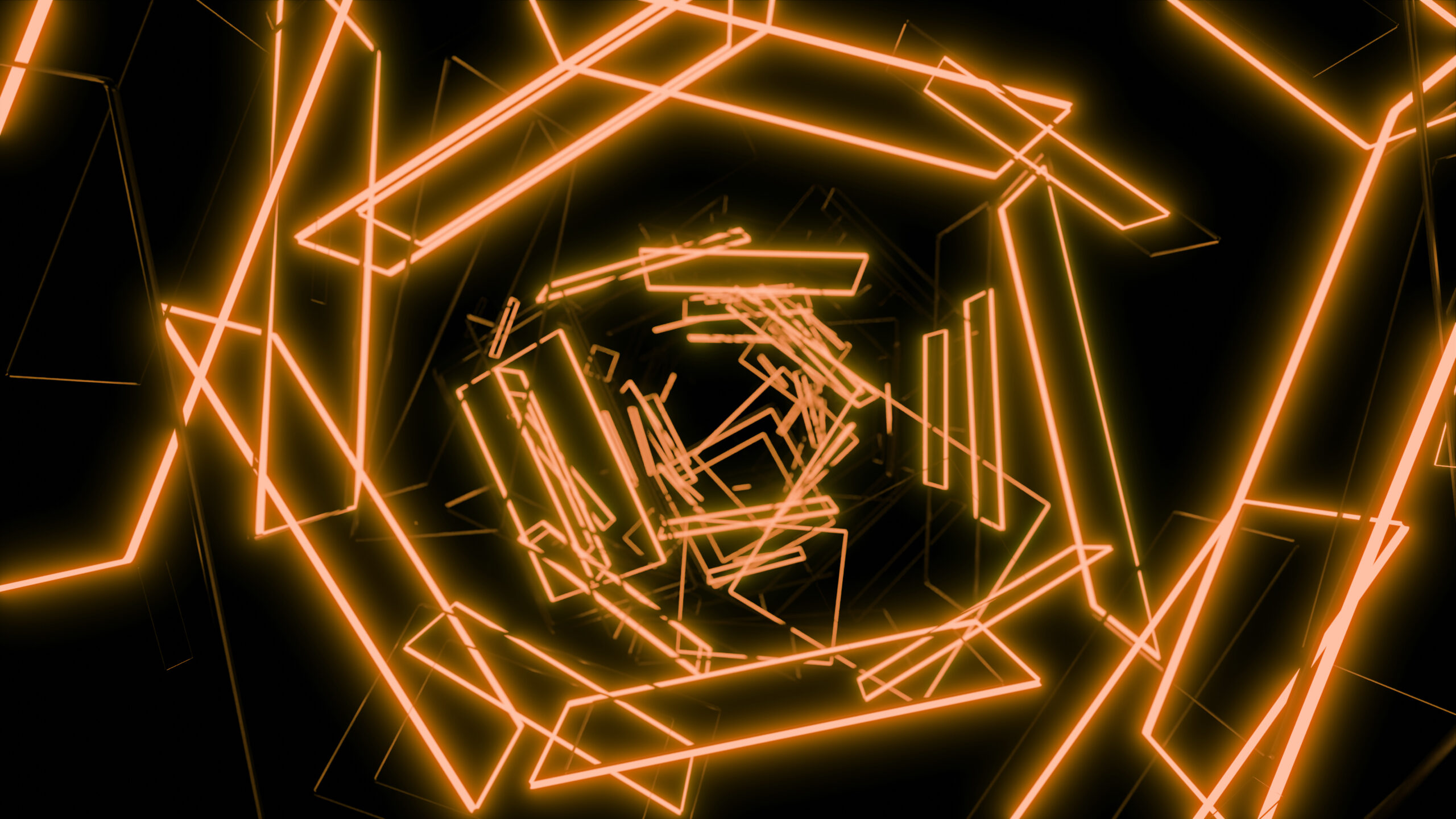
データが取れるようになり、AIやアルゴリズムによる最適化技術が進歩したことで、広告は論理的に制御可能なものとして扱われるようになりました。
ターゲットを絞り、配信タイミングを調整し、クリエイティブをテストし、数値を見ながら改善を重ねる。このサイクルを回していけば、成果は自ずとついてくるはずだ。そういう前提が、広告業界には広く共有されています。
もちろん、この考え方には一定の合理性があります。
実際、データに基づいた運用改善によって成果を上げている事例は数多くあります。しかし、この前提には、ひとつの暗黙の了解が含まれています。それは、正しく設計すれば、正しい結果が得られるはずだ、という了解です。入力と出力の関係が明確であり、条件を整えれば結果は予測できる。広告を機械のように捉える見方とも言えます。
しかし現実は素直ではない
ところが、現実の広告は、そこまで単純ではありません。
同じクリエイティブを使っても、媒体が変われば反応が変わります。条件を揃えても、時期が違えば結果が変わります。昨年うまくいった施策を今年も試してみたら、まったく反応がなかったという経験をした方もいるのではないでしょうか。
数値上は改善しているはずなのに、売上には結びつかない。クリック率は高いのに、ブランドの好意度は上がらない。こうした現象を、単なる運用ミスや精度不足として片付けてしまうのは簡単です。しかし、それでは広告の本質には辿り着けません。むしろ、広告という仕組みそのものが、最初から割り切れない性質を内包していると考える方が、現実に近いのではないでしょうか。
量子論という補助線
ここで、物理学の世界から、ひとつの考え方を借りてみます。量子論です。
量子論は、原子や電子といった極めて小さな世界を扱う物理学の理論です。20世紀の初頭に生まれ、現代の科学技術の基盤となっています。スマートフォンも、コンピュータも、量子論なしには存在しません。
ただ、ここで量子論を持ち出すのは、物理学の話をしたいからではありません。量子論の根底にある発想が、広告の揺らぎを考えるうえで、ひとつの補助線になると考えたからです。
観測されるまで世界は確定しない
私たちが普段暮らしている世界では、物体は一つの状態を持っています。机は机であり、椅子は椅子です。リンゴは、見ていないときでもリンゴとしてそこにあるはずです。
しかし、量子の世界では、事情が異なります。電子のような粒子は、観測されるまで、特定の位置や状態を持っていないと考えられています。
これは、私たちの直感に反する話です。
見ていなくても、そこにあるはずだ。そう考えるのが自然です。しかし、量子論が示しているのは、観測という行為そのものが、世界の状態を確定させる、という考え方です。観測される前は、粒子はどこにいるのか決まっていない。複数の可能性が、同時に存在している。そして、観測された瞬間に、ひとつの結果として確定する。これが量子論の基本的な発想です。
重ね合わせという考え方

複数の可能性が同時に存在している状態を、物理学では「重ね合わせ」と呼びます。重ね合わせは、曖昧さや不完全さを意味しているわけではありません。可能性が並行して存在しているという構造そのものが、量子の世界の前提なのです。
有名な思考実験に、シュレーディンガーの猫というものがあります。
放射性元素の崩壊を検知すると猫が死ぬ仕掛けのある箱に、猫を入れる。1時間後、箱を開けるまで、猫は生きているのか死んでいるのかわからない。量子論的に言えば、観測するまで、猫は生きている状態と死んでいる状態が重ね合わさっている、ということになります。これは直感的には奇妙な話ですが、量子の世界では、こうした重ね合わせが実際に起きていることが、実験によって確認されています。
広告の意味はいつ決まるのか
この考え方を広告に当てはめてみます。
広告は、作られた時点で、ひとつの意味を持っているように思えます。こういうメッセージを、こういう人に、こういう形で届けたい。設計者の意図は明確です。しかし、その広告が実際に届いたとき、受け取る人がどのように解釈するかは、設計者がコントロールできるものではありません。
同じ広告でも、見る人によって、感じ方は変わります。その日の気分、体調、置かれている状況、直前に見た情報、過去の経験。こうした要素が複雑に絡み合い、広告は解釈されます。ある人には好意的に受け取られ、別の人には無関心に流され、また別の人には不快に感じられるかもしれません。広告の意味は、配信した瞬間に確定するのではなく、受け取られた瞬間に立ち上がるものです。
そう考えると、広告もまた、観測されることで初めてひとつの姿を持つ存在だと言えるかもしれません。設計された時点では、複数の意味の可能性を内包している。誰に、どんな文脈で、どんな状況で受け取られるかによって、どの意味が立ち上がるかが決まる。量子論の重ね合わせと、構造的に似たところがあります。
2進数のフィルタと人の認知のあいだ
広告は、コンピュータの上で設計され、配信されます。
デジタル広告はもちろん、交通広告やテレビCMの出稿計画も、今ではコンピュータ上のデータをもとに決められています。コンピュータの世界は、すべてが0と1でできています。オンかオフか。配信するかしないか。表示されるかされないか。クリックされたかされなかったか。判断は常に二択です。
広告は0と1で設計される
広告の設計プロセスを分解してみると、いくつもの二択判断が積み重なっていることがわかります。
ターゲットは都市部か、地方か。BtoCか、BtoBか。予算は確保できるか、できないか。長期で続けるか、短期で勝負するか。動画を使うか、静止画にするか。こうした二択をひとつひとつ決めていくことで、広告の形が定まっていきます。
配信の段階でも同様です。この条件に合う人に配信するか、しないか。この時間帯に出すか、出さないか。このサイトに掲載するか、しないか。アルゴリズムが瞬時に判断を下し、広告は人のもとに届きます。すべてが0か1かのフィルタを通過した結果です。
フィルタを重ねても決められないもの
ターゲット条件、配信タイミング、媒体特性、クリエイティブ、評価指標。それぞれが0か1かでふるいにかけられ、広告は人に届きます。フィルタの精度は年々上がっています。狙った人に、狙ったタイミングで、狙った広告を届けることは、技術的にはかなりのところまで可能になっています。
しかし、そのフィルタをいくつ重ねても、最終的に人がどのように受け取るかを完全に決めることはできません。
広告が届いた瞬間、その人が何を考えていたか。どんな気分だったか。何を求めていたか。これらは、フィルタでは捕捉できない領域です。むしろ、フィルタを重ねるほど、どこかで揺らぎが生まれます。精度を上げれば上げるほど、予測と現実のあいだに、小さなズレが蓄積していくのです。
揺らぎの正体

この揺らぎは、設計の甘さや運用のミスによって生まれるものではありません。0と1の判断を積み重ねる構造そのものが、最終的に連続的で曖昧な人の認知と接続されることで、必然的に生じるものです。
量子論には「揺らぎ」という概念があります。
どれだけ精密に条件を整えても、結果は確率的にしか語れない領域が残る。これは誤差やノイズではなく、理論そのものに組み込まれた性質です。
広告の世界でも、同じことが言えます。広告は2進数で設計されながら、2進数では完結しない場所に着地します。デジタルの世界で生まれた広告が、アナログな人の心に届く。そのインターフェースにおいて、揺らぎは避けられないものなのです。
ここで誤解してはいけないのは、データやアルゴリズムを否定しているわけではない、という点です。
データは、広告を効率よく届け、改善していくための重要な手段です。AIや最適化技術は、広告運用を大きく前進させてきました。しかし、それらはあくまで設計を支える道具であり、広告の意味そのものを決定する存在ではありません。最後の一歩は、人の解釈に委ねられています。
再現性を求めるほど失われるもの
広告の現場では、しばしば再現性が求められます。
同じ条件で、同じ成果を出せること。これは組織としてはとても合理的な要求です。説明もしやすく、意思決定も速くなります。成功パターンを見つけ、それを横展開していく。効率的な運用とは、そういうものだと考えられています。
安定した広告は良い広告か
再現性を高めるためには、条件を固定する必要があります。
ターゲットを絞り、表現を統一し、評価軸を限定する。変数を減らし、コントロールできる範囲を広げていく。こうして広告は、だんだんと安全な形に整えられていきます。その結果、確かに数値は安定します。予測と実績のブレが小さくなり、報告もしやすくなります。
しかし、ここで立ち止まって考える必要があります。
安定した広告とは、本当に良い広告なのでしょうか。あるいは、それは単に説明しやすい広告に過ぎないのではないでしょうか。数値が安定しているということは、想定の範囲内で推移しているということです。大きく外すことはないけれど、大きく跳ねることもない。そういう広告が増えていくと、全体として均質化が進みます。
意味を固定することの代償
量子論的な視点で見ると、安定とは可能性をひとつに固定することです。
確定した状態は扱いやすく、管理もしやすい。しかし、そこには新しい意味が生まれる余地がほとんど残りません。重ね合わせの状態を解消し、ひとつの結果に収束させることで、予測可能性は高まりますが、同時に、それ以外の可能性は消えてしまいます。
広告も同様です。意味をひとつに決め切った広告は、誤解されにくい一方で、深く解釈されることも少なくなります。受け取り方の幅を狭めることで、リスクは減りますが、記憶に残る確率も下がります。誰にでも同じように届く広告は、誰の心にも深く刺さらない広告になりがちです。
一方で、揺らぎを内包した広告はどうでしょうか。
解釈の余地がある広告は、人によって受け取り方が変わります。ある人には共感として届き、別の人には違和感として残るかもしれません。そのすべてが、短期的な数値として可視化されるわけではありません。しかし、その曖昧さの中にこそ、記憶に残る広告や、人に語られる広告が生まれる余地があります。
ブランドが測りにくい理由
ブランド広告の効果が測りにくいと言われる理由も、ここにあります。
ブランドとは、明確な0か1かで測れるものではありません。好意、信頼、親近感、憧れ。こうした要素は、連続的で、時間をかけて形成されていきます。今日見た広告が、すぐに購買につながるわけではありません。しかし、何度も目にするうちに、少しずつ印象が積み重なり、いつか選ばれる理由になる。ブランドの効果とは、そういうものです。
量子論的に言えば、ブランドとは常に重ね合わせの状態にあると言えます。見る人の経験や立場によって、評価は揺れ動きます。同じブランドでも、ある人にとっては信頼の象徴であり、別の人にとっては無関心の対象です。この揺らぎを無理に固定しようとすると、ブランドの持つ豊かさが損なわれてしまいます。
揺らぎを内包する広告設計
これまで見てきたように、広告には本質的に揺らぎがあります。0と1で設計されながら、0と1では完結しない。この構造を理解したうえで、これからの広告をどう考えればよいのでしょうか。
解釈の余地を残すということ
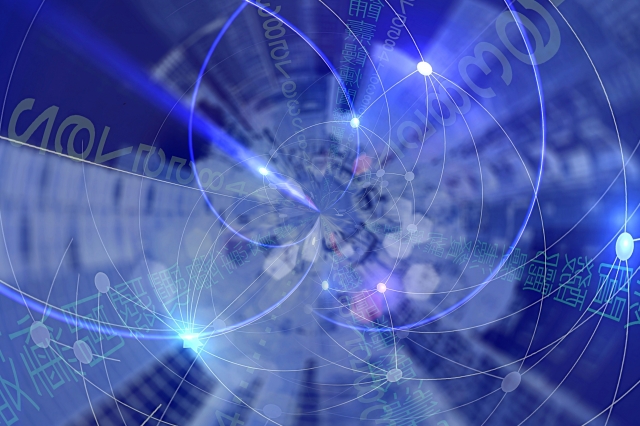
ひとつの方向性は、解釈の余地を意識的に残すことです。
メッセージを完全に固定するのではなく、受け取る人が自分なりに意味を見出せる余白を設計に組み込む。すべてを説明し尽くすのではなく、想像の余地を残す。こうした広告は、短期的な数値では測りにくいかもしれません。しかし、人の記憶に残り、語られる広告は、往々にしてそういう余白を持っています。
もちろん、余白を残すことと、曖昧なまま放置することは違います。意図のない曖昧さは、単なる伝わりにくさになってしまいます。大切なのは、どこを固定し、どこを開くかを意識的に設計することです。伝えたいことの核は明確にしつつ、その周辺には解釈の幅を持たせる。このバランスが、揺らぎを活かす広告設計のポイントになります。
評価の時間軸を広げる
揺らぎを前提にすると、広告の評価の仕方も変わってきます。短期的な数値だけで判断しようとすると、揺らぎはノイズにしか見えません。今週の数字が良かったか悪かったか。先月と比べてどうだったか。こうした視点だけでは、広告が持つ長期的な効果を見落としてしまいます。
人の記憶や印象は、すぐには数値に現れません。今日見た広告が、半年後の購買に影響を与えることもあります。繰り返し目にするうちに、少しずつ信頼が積み重なっていくこともあります。そうした時間をかけて形成されるものは、週次や月次のレポートには載りにくい。だからといって、存在しないわけではありません。
評価の時間軸を広げることで、揺らぎの中にある意味が見えてきます。短期で測れるものと、長期でしか見えないもの。その両方を視野に入れることが、揺らぎを内包した広告設計の第一歩です。
対話から始まる広告づくり
揺らぎを前提にした広告設計において、大切なのは対話です。
広告の正解は、最初から決まっているわけではありません。作り手の意図と、受け手の解釈が出会うところに、広告の意味が生まれます。その出会いを豊かなものにするためには、一方的に発信するだけでなく、反応を見て、考え、また発信するというサイクルが必要です。
社内での対話も同様です。広告の設計段階で、異なる視点を持つ人と議論することで、思い込みが解消されたり、新しいアイデアが生まれたりします。再現性や効率だけを追い求めると、こうした対話の時間は削られがちです。しかし、割り切れないものに向き合うには、対話の時間を確保することが必要です。
答えをひとつに決め切れない問いこそ、対話から始まります。
もし、データどおりに設計しているのに成果が安定しない、あるいは最適化を重ねるほど広告が均質化していると感じているのであれば、一度立ち止まって、割り切れなさを前提に広告を見直してみる価値があります。
私たちは、広告の設計や運用だけでなく、こうした対話のきっかけづくりも大切にしています。何か壁打ちしてみたいことがあれば、お気軽にお問い合わせフォームからご連絡ください。