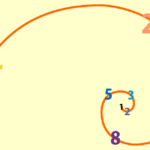2026年2月18日
マーケティング昭和の看板文字がZ世代に刺さる理由 手描き文字を広告に活かすヒント

街を歩いていると、古い商店の軒先や、長く使われてきた看板の文字に、ふと目が止まることがあります。
線の太さが均一でなかったり、文字ごとにわずかな歪みがあったり。現代のデジタルフォントとは明らかに違う、どこか温かみのある表情を持った文字たちです。
こうした昭和期に多く見られた手描きの看板文字が、いまZ世代を中心とした若い世代から「エモい」「味がある」と支持されています。2024年にトイズキングが実施した調査によると、Z世代の6割以上がレトロ文化に「興味がある」と回答しています。レトロ文化の魅力として挙げられた理由の上位には、「現代の製品にはない独特のデザインやテイスト」や「現代社会にはない不完全さ」といった項目が並びました。
SNSでは、街角で見つけたレトロな看板の写真が次々と共有されています。Instagramで「レトロ」と検索すると、約361万件もの投稿がヒットします(2026年1月現在)。純喫茶や昔ながらの銭湯、町の電器屋さんなど、かつては「古い」と敬遠されがちだった場所が、若い人たちの間で人気スポットになっている光景も珍しくありません。
不思議なのは、デジタルネイティブと呼ばれる世代が、自分たちが生まれる前のアナログな表現に強く惹かれているという点です。生まれたときからスマートフォンやインターネットに囲まれて育ち、最新のデザインやテクノロジーに慣れ親しんでいるはずの世代が、なぜ半世紀も前の手描き文字に心を動かされるのでしょうか。単なる懐古趣味では説明しきれない、何か別の理由がありそうです。
ここでは、昭和レトロな看板文字がなぜ現代の若い世代に響くのか、その背景にある視覚的・心理的な要因を整理しながら、広告表現やブランドづくりにどう活かせるかを掘り下げていきます。
街の風景として残ってきた手描き文字
昭和の看板文字は、単に店名を伝えるための道具ではありませんでした。街並みの一部として人々の目に触れ、意識しないうちに記憶に残っていく。そんな役割を静かに果たしてきた存在です。まずは、こうした文字がどのような特徴を持ち、なぜ今も残っているのかを見ていきます。
整っていないからこそ印象に残る
昭和期の看板文字には、現代のフォントにはない特徴があります。
線の太さにばらつきがあり、文字の傾きも一定ではありません。同じ「あ」という文字でも、書くたびに少しずつ表情が変わります。デザインとして見ると、決して洗練されているとは言いにくいものも多くあります。
しかし、その不揃いさが、かえって見る人の記憶に残りやすくしています。人間の脳は、均一で予測可能なものよりも、少し違和感のあるものに注意を向ける傾向があります。繰り返し見る同じ刺激には反応が鈍くなる一方、わずかでも違いがあるものには敏感に反応します。手描き文字の微妙な揺らぎやクセは、視覚的な「引っかかり」となって、印象に残りやすくなるのです。
現代の街を歩くと、チェーン店の看板はどれも同じフォント、同じ色、同じレイアウトで統一されています。効率的で、ブランドの一貫性を保つには理にかなった方法です。しかし、その結果として、どの街に行っても同じ風景になり、個々の店舗の印象が薄れてしまうという側面もあります。昭和の看板文字が持っていた「一つひとつが違う」という特性は、現代では逆に希少価値を持つようになっています。
レトロを狙ったわけではない文字たち

いま私たちが「昭和レトロなフォント」と呼んでいるものの多くは、当初からレトロな雰囲気を意識して作られたわけではありません。看板職人や店主、時にはその知人や家族などが、目立つこと、伝わることを優先して、その場で描いた文字がほとんどです。
当時は、看板を作るにもパソコンやデザインソフトはありませんでした。専門の看板屋に依頼するか、自分たちで手描きするか。多くの小さな商店では、コストを抑えるために後者を選びました。ペンキと刷毛、あるいは筆を使って、店主自らが文字を描く。上手い下手よりも、とにかく読めること、目立つことが優先されました。
デザインとして計算されたものではなく、必要に迫られて生まれた文字。その中で、使われ続け、街の風景として定着したものだけが、現在まで残っています。「昭和レトロ」というのは様式の名前ではなく、時間をかけて選ばれてきた結果に対する後付けの呼び名なのです。
この視点に立つと、看板文字は単なる懐かしい表現ではなく、数十年にわたって機能し続けてきた実績のある視覚表現として捉えることができます。見る人に受け入れられ、街の一部として馴染み、店とともに年月を重ねてきた。その「使われ続けた」という事実自体が、一つの価値を持っています。
人の手が残した痕跡という価値
手描きの看板文字には、一度描いたらやり直しがきかないという性質があります。
下書きはあったかもしれませんが、本番の一発勝負で仕上げられたものがほとんどです。失敗したらペンキを塗り直してもう一度、という手間を考えると、緊張感を持って一筆一筆を運んでいたことが想像できます。
その緊張感や勢いが、文字の表情として残っています。線の走り方、力の入れ具合、筆を離すときの動き。すべてが、描いた人の身体の動きを記録しています。寒い日に描いたのか、急いでいたのか、丁寧に仕上げようとしたのか。そうした背景が、文字の佇まいから感じ取れることがあります。
デジタルフォントは何度でも修正できますし、完璧に揃えることができます。1ピクセルのズレも許さない精密さで、いつでも同じ品質の文字を出力できます。しかし、その完璧さゆえに、人の存在を感じにくいという側面もあります。誰が作っても同じ結果になるという均質性は、効率的である反面、個性や温度感を失わせます。手描き文字に宿る「取り返しのつかなさ」は、見る人に人間の存在を意識させ、親しみや信頼感につながっているのです。
ほっかほっか亭のロゴが示すもの
昭和レトロな看板文字の代表例として、ほっかほっか亭のロゴがあります。全国の街角で長年使われてきたこの文字は、多くの人にとって見慣れた存在です。2025年11月、テレビ番組の調査によってその成り立ちが明らかになりました。この事例から、看板文字の本質を考えてみます。
約50年使われてきた文字の出自
ほっかほっか亭は1976年、埼玉県草加市で第1号店を開業しました。赤と黄色の温かみのある配色に、手描き風の柔らかい文字。このロゴは、創業から現在まで約50年にわたって使い続けられています。日本全国どこでも見かける、馴染み深い文字です。
長らく「誰が描いたのかわからない」とされてきたこのロゴですが、2025年11月に放送されたテレビ番組「探偵!ナイトスクープ」の調査によって、その出自が判明しました。当初は「創業時のアルバイト学生が描いた」という話が社内に伝わっていましたが、調査の結果、実際の経緯は異なることがわかりました。
1号店のロゴを描いたのは、当時内装業を営んでいた大西さんという人物でした。創業者の田渕さんから新しい弁当屋のロゴを相談され、お弁当から立ち上る湯気をイメージして文字を書いたそうです。その後、フランチャイズ展開にあたってデザイン会社「拓創」がブラッシュアップを加えましたが、文字の基本的な骨格は、最初に大西さんが描いたものが受け継がれています。
専門のデザイナーではない人が描いた文字
注目すべきは、このロゴを最初に描いたのが、グラフィックデザイナーではなく、うどん屋を営んでいた人物だったという点です。飲食店の店主として、日常的に店の看板やメニュー、値札などの文字を目にし、書いてきた経験があったと考えられます。「お客さんに伝わる文字」「目を引く文字」を、肌感覚で知っていた人です。
専門家が市場調査やコンセプト設計を経て練り上げたデザインではなく、現場感覚から生まれた文字。計算よりも直感、理論よりも経験が優先された結果です。その親しみやすさ、あたたかさが、結果として約半世紀にわたって使われ続ける理由の一つになったのかもしれません。
「長く使われるロゴを作ろう」と最初から意図していたわけではなく、「新しい弁当屋の看板を書いてほしい」という依頼に応えて、日常の延長線上で生まれた文字。それが、気づけば50年近く、数百万人の目に触れ続けている。この事実は、看板文字が持つ力を考えるうえで示唆に富んでいます。
残ったものがレトロと呼ばれる
ほっかほっか亭のロゴは、いま見ると「昭和レトロ」の代表例のように感じられます。手描き風の温かみ、少し丸みを帯びた文字、赤と黄色の配色。どれも「レトロ」という言葉から連想される要素を備えています。
しかし、1976年当時は、単に「新しくできた弁当屋の看板」でした。当時の感覚では、ごく普通の、ありふれた文字だったはずです。周囲にも同じような手描きの看板がたくさんありました。
時間が経ち、周囲の風景が変わり、デジタルフォントが主流になった現代において、この手描き文字が相対的に「レトロ」に見えるようになった。つまり、「レトロだから残った」のではなく、「残ったものが後からレトロと呼ばれるようになった」という順序です。
この視点は、これからの広告表現を考えるうえでも重要です。いま「最新」とされているデザインも、数十年後にはレトロになります。流行を追いかけるよりも、長く使われる可能性のある表現を選ぶこと。時間の経過に耐えられる骨格を持った表現を作ること。その判断基準として、ほっかほっか亭のロゴは一つの参考になります。
Z世代が昭和の看板文字に惹かれる背景
昭和の看板文字に対して、Z世代は「懐かしい」ではなく「新しい」「エモい」という反応を示します。自分たちが生まれる前の時代の表現に、なぜ強い関心を持つのか。その背景には、デジタル環境で育った世代ならではの感覚があります。
完璧すぎるものへの違和感

Z世代は、幼い頃からスマートフォンやパソコンに囲まれて育ってきました。
画面上の文字は常に整い、画像は加工され、ノイズはできるだけ取り除かれています。写真は撮った後にフィルターをかけ、肌を滑らかにし、背景をぼかすことができます。見るものすべてが最適化された環境が当たり前になっています。
その一方で、過度に整えられた表現に対して、無意識のうちに距離を感じている側面もあるようです。2024年のトイズキングの調査では、レトロ文化の魅力として「現代社会にはない不完全さ」を挙げた人が34.7%にのぼりました。完璧に加工されたインフルエンサーの写真よりも、あえて粗さを残したスナップ写真のほうが「本物っぽい」と感じる。フィルターをかけすぎた画像は「嘘っぽい」「信用できない」と受け止められる。そうした感覚を持つ人が増えています。
昭和の看板文字が持つ不揃いさは、この世代にとっては欠点ではなく、むしろ「人が関わった証拠」として受け止められます。線の太さが揃っていないこと、文字ごとに微妙に表情が違うこと、色あせや傷があること。これらは、加工されていない、ありのままの姿として認識されます。だからこそ、信頼感やリアリティにつながるのです。
SNSで共有される「発見」の体験
Z世代の情報行動を語るうえで、SNSの存在は欠かせません。
InstagramやTikTok、Xなどのプラットフォームで、日常的にコンテンツを発信し、共有しています。昭和の看板文字は、写真に撮ったときに強い存在感を発揮します。
文字そのものだけでなく、背景の古い建物、色あせた看板、錆びたトタン、周囲の空気感まで、一枚の画像に収まります。その場所の歴史や時間の流れを、言葉で説明しなくても伝えることができます。「映える」という言葉がありますが、レトロな看板には独特の映え方があります。
SNSで共有される看板文字の写真は、単なるデザイン紹介ではありません。「この街にこんな場所があった」「この文字にはこんな歴史がありそうだ」という物語ごと伝わります。Z世代が「エモい」と表現する感情の多くは、こうした物語性に対する反応です。きれいなだけでは感動しない。そこに物語や文脈があるから、心が動く。
また、レトロな看板を「見つけた」という体験自体に価値があります。誰かが作った最新コンテンツを消費するのではなく、もともとそこにあったものを自分の視点で再発見する。他の人が見逃していたものを自分だけが気づいた、という感覚。この「発見」の喜びが、共有文化と相性よく合っています。
知らない時代だからこそ新鮮に映る
Z世代にとって、昭和は教科書や映像で見る「歴史」の一部です。
1990年代後半から2010年代前半に生まれた世代にとって、昭和という時代は直接体験したことのない過去です。親や祖父母の話、テレビの特集番組、映画やドラマの中でしか触れたことがありません。
親世代にとっては懐かしさを伴う表現であっても、Z世代にとっては先入観のないビジュアルとして映ります。「古臭い」「ダサい」といったネガティブな印象が薄く、純粋に形として、色として、雰囲気として評価することができます。
「古い」と「新しい」は、見る人の経験によって変わります。何度も見たことがあるものは古く感じ、初めて見るものは新しく感じる。体験したことのない時代の表現は、その人にとっては未知のもの。だからこそ、昭和の看板文字は、Z世代にとって「新鮮なデザイン」として受け止められるのです。
復古的な演出ではなく、純粋に形として評価されている。この点は、広告表現を考えるうえでも見逃せないポイントです。若い世代に向けて「懐かしさ」を訴求しても響きません。彼らにとっては懐かしくないからです。しかし、「見たことのない面白さ」として訴求すれば、興味を持ってもらえる可能性があります。
広告表現に活かすためのヒント
昭和レトロな看板文字の再評価は、感性の話だけではありません。そこには、現代の広告やブランドづくりに応用できる具体的な示唆が含まれています。実務の現場でどう活かせるか、いくつかの観点から整理します。
印象に残ることを優先する選択
広告表現において、読みやすさや統一感は大切な要素です。
ブランドガイドラインに沿って、指定されたフォント、指定された色、指定されたレイアウトで制作する。企業としての一貫性を保つには、こうしたルールが必要です。
しかし、すべてを整えた結果、どこにでもある表現になってしまうことも少なくありません。きれいにまとまっているけれど、記憶に残らない。他社の広告と並べたとき、区別がつかない。そんな広告を見かけることはないでしょうか。
昭和の看板文字が教えてくれるのは、「整っていなくても、印象には残る」という事実です。むしろ、少しの不揃いさが視覚的な引っかかりになり、記憶に残りやすくなることがあります。
特に店舗の看板や、短時間で目に入る屋外広告や交通広告では、洗練よりも印象を優先する判断が有効な場面があります。通り過ぎる一瞬で目に留まり、「あれは何だろう」と思わせる力。すべてをデジタルフォントで統一するのではなく、手描き風の要素を取り入れることで、他との差別化を図れる可能性があります。
余白や曖昧さを残す設計
広告を作る側は、伝えたいことをできるだけ明確に、漏れなく伝えようとします。
商品の特徴、価格、キャンペーン情報、問い合わせ先。限られたスペースに、できるだけ多くの情報を詰め込もうとする。その姿勢は正しいのですが、情報を詰め込みすぎると、受け手が解釈する余地がなくなってしまいます。
看板文字の多くは、意味を詰め込んで作られたものではありません。店名と業種がわかればいい、という最低限の情報だけで成り立っています。「田中酒店」「山本電機」「さくら理容室」。それ以上の説明はありません。その「余白」があるからこそ、見る人はそこに自分なりの意味や感情を重ねることができます。
この店は何年くらい続いているのだろう。どんな人がやっているのだろう。昔はもっと賑わっていたのかな。そうした想像を膨らませる余地があることで、見る人の中に物語が生まれます。すべてが説明されていたら、そうした余韻は生まれません。
特に若い世代に向けたコミュニケーションでは、「完成された答え」を提示するよりも、想像の余地を残す設計のほうが響くことがあります。すべてを説明しきらない、という選択肢も検討に値します。
若い世代にとっての「新しさ」とは何か

Z世代向けの広告というと、最新のトレンドやSNS文脈を意識しがちです。TikTokで流行っている音楽を使う、インフルエンサーを起用する、最新のミームを取り入れる。そうした手法は一定の効果がありますが、同時に多くの企業が同じことをするため、埋もれやすくもあります。
昭和の看板文字がZ世代に支持されている事実は、「新しさ」の定義を考え直すきっかけになります。若い世代にとって未体験の表現であれば、それは十分に新鮮なビジュアルになり得ます。最新であることだけが新しさではない。その人にとって初めてであれば、それは新しいのです。
過去の表現をそのまま模倣するのではなく、なぜその文字が長く残ったのか、どの要素が機能していたのかを分解し、現代の文脈に合わせて再構築する。そうしたアプローチが有効です。手描きの揺らぎ、色の組み合わせ、文字のバランス。それぞれの要素を取り出して、現代の媒体やターゲットに合わせて調整する。
表面的に「レトロ風」を演出するのではなく、手描き文字が持っていた温度感や人間味をどう再現するか。その視点で考えると、表現の幅が広がります。
長く使われる表現という視点
広告は、短期的な効果を求められることが多い仕事です。
キャンペーンごとに新しいビジュアルを作り、反応を見て、また次を作る。そのサイクル自体は悪いことではありません。市場の変化に対応し、常に新鮮さを保つためには、継続的な更新が必要です。
ただし、ブランド全体を考えたとき、「長く使われる表現をどう作るか」という視点も必要になります。ほっかほっか亭のロゴは、約50年にわたって使われ続けています。その間、時代に合わせて微調整はされていますが、基本的な骨格は変わっていません。文字の形、色の組み合わせ、全体の印象。核となる部分は守られてきました。
最初から完璧を目指すよりも、使いながら育てていく余地を残すこと。細部まで作り込みすぎず、時間とともに馴染んでいける柔軟性を持たせること。その結果として、時間をかけて定着し、後から価値が認められる可能性があります。看板文字は、「残る表現とは何か」を考えるための、一つの実例です。
まとめ
昭和レトロな看板文字は、単なる懐かしさの象徴ではありません。街の風景の中で使われ、選ばれ、残り続けてきた結果として、いま私たちの前にあります。
ほっかほっか亭のロゴが示すように、専門のデザイナーではなく、現場に近い人の感覚から生まれた文字が、結果として約半世紀にわたって使われ続けることもあります。「レトロだから価値がある」のではなく、「長く機能し続けた結果、レトロと呼ばれるようになった」という順序を押さえておくことが大切です。
デジタル環境が整い、誰もが同じようなフォントや表現を使える時代だからこそ、手描きの文字や、人の存在を感じさせる表現には、独自の強みがあります。均一で整った表現があふれる中で、少しの不揃いさや温度感が、かえって目を引く要素になっています。
Z世代を含む若い世代にとって、「新しさ」とは必ずしも最新であることではなく、自分にとって未体験であることなのかもしれません。知らない時代の表現は、先入観なく受け止めることができるからこそ、新鮮に映ります。古さを隠すのではなく、価値として活かすという発想の転換が、現代の広告表現にも求められています。
広告やブランドの表現を見直す際、すべてを洗練させるのではなく、あえて余白や人間味を残すという選択肢もあります。どの要素を整え、どこに揺らぎを残すのか。その判断が、記憶に残る表現につながっていきます。
当社では、交通広告や屋外広告を中心に、70年以上にわたって広告制作に携わってきました。看板やロゴ、店舗サインなどの制作においても、単なるトレンドの踏襲ではなく、背景や文脈を踏まえた表現をご提案しています。
長く使われる表現を目指したブランディングや、若い世代に届く広告表現について検討されている場合は、お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。